 知らないうちにこんなものが出来ていました。
知らないうちにこんなものが出来ていました。
先日の和歌山で白は配布済み。
あとは少し青・ピンクがあります。
ちなみにこの写真。
「雨のみち」を書いていただいた方のブログより
勝手に拝借させていただきました。
かなり高級感があるように見えますね。
さて実物は・・・

日々心動かされたことを記していきます
 知らないうちにこんなものが出来ていました。
知らないうちにこんなものが出来ていました。
先日の和歌山で白は配布済み。
あとは少し青・ピンクがあります。
ちなみにこの写真。
「雨のみち」を書いていただいた方のブログより
勝手に拝借させていただきました。
かなり高級感があるように見えますね。
さて実物は・・・
「ハーブ&おいしい野菜塾」の方にアドバイスを頂きました。
ゴーヤーに花が咲いたとのことですが、
その花は摘んで下さい。それは、通称「バカ花」と呼びます。
そのままにしても実も成りませんし、株が弱ってしまいます。
5月,6月は株を強く育てる事を心がけるとよいと思います。
早速、花は摘んでおきたいと思います。
またとある学校の先生からは
新聞の記事によると記録的日照不足に注意とあります。
平年比、東京は67%だそうです。
そういえば、○×小のアサガオは双葉の様子がどうもおかしいのです。
種を大袋で購入したため、 その種に問題があったのかと考えましたが、
日照不足の影響は考えられますね。
我が家の緑のカーテンは東南向き。
朝日が気持ちよく当たっていますが、15時過ぎには日陰になってしまいます。
今のところは問題なさそうですが・・・。
一度見学しているこの建物。
その後の様子を見に行きました。 すでに隣地(空き地)の木の葉が緑のカーテンになっています。
すでに隣地(空き地)の木の葉が緑のカーテンになっています。
緑のカーテンを通じて入ってくる風はとても気持ちが良いです。
溜めた雨を散水すると更にヒヤッとしてきます。
障子に映る影も綺麗ですね。
 窓の外に水栓があるのが見えますか?
窓の外に水栓があるのが見えますか?
なぜこんなところについているのでしょうか?
実はこれは前回になかった「雨水栓」
どこに窓についているかというと・・・・
 雨水栓から雨水を浴槽に入れ追い炊き機能で沸かすとのこと。
雨水栓から雨水を浴槽に入れ追い炊き機能で沸かすとのこと。
まだ引き回したばかりなので、利用するのはこれから。
「肌に優しい」「泡立ちがよい」「美人になる」などいろいろ効果があるだろうとのこと。
どんな報告があるのか今から楽しみです。
但し1回で溜めた雨水を大量に使ってしまうのが残念との話。
2tの雨水タンクが一杯の時にトライしてみるとのこと。
そんな話をしていると夕立が・・・。
ますます雨の降る日が楽しみになりそうですね。
 区役所でも緑のカーテンがスタートしました。
区役所でも緑のカーテンがスタートしました。 プランターには自動灌水装置。
プランターには自動灌水装置。
紐を使ってツルをネットまで誘引しています。 駐車場の前なのであまり良い環境ではありません。
駐車場の前なのであまり良い環境ではありません。
出来れば「緑のカーテン」前だけでも頭から突っ込んで駐車するようにしてほしいですね。
遅くなりましたが、見学したモデルハウスの報告です。
 木と金属と吹きつけで仕上げた外観。
木と金属と吹きつけで仕上げた外観。
軒の出もしっかりあるので、良い表情になっています。 こんな雨戸も風も通って良いですね。
こんな雨戸も風も通って良いですね。
 室内も木がふんだんに使われています。
室内も木がふんだんに使われています。 2階の事務所も気持ちが良さそうですね。
2階の事務所も気持ちが良さそうですね。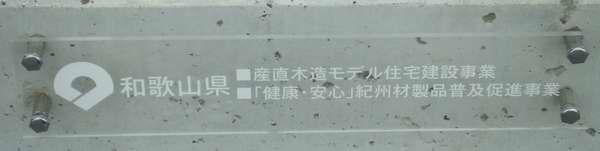 県の推奨事業のようです。
県の推奨事業のようです。

 そしてなんと「緑のカーテン」も実践されています。
そしてなんと「緑のカーテン」も実践されています。 夏にはゴーヤーがたくさん取れそうですね。
夏にはゴーヤーがたくさん取れそうですね。