2回目の勉強会が9/10に開催され、参加しました。
現在、地域コミュニティーが崩壊していると云われていますが、
そんな中、共同体としての生活の意義と実現の難しさを感じました。
公と個のバランスがとれた地域社会。
相互扶助・相互秩序が共同体をベースに育まれている地域社会。
我々建設に携わるものにもその役割の一端が果たせますね。

日々心動かされたことを記していきます
2回目の勉強会が9/10に開催され、参加しました。
現在、地域コミュニティーが崩壊していると云われていますが、
そんな中、共同体としての生活の意義と実現の難しさを感じました。
公と個のバランスがとれた地域社会。
相互扶助・相互秩序が共同体をベースに育まれている地域社会。
我々建設に携わるものにもその役割の一端が果たせますね。
 見学会のあと、場所を変えて、
見学会のあと、場所を変えて、
山と家を結ぶネットワークでつくる「木の家」フォーラムに参加しました
以下に感じたことを記します。
・伐採して使わないと50年後には森がなくなる
木の成長に合わせた伐採と次の木を育てる循環が必要だがそれが出来ていない
・CO2の固定化には、国産材を使った住まいづくりが効果アリ
・木は別の素材と共に使うことで更に木の良さが伝わる(例えば金属)
・いつも尻拭いをさせられているのは工務店(例えば今回のアスベストも)
・木の使える範囲が広がっている(準防火地域での外壁材など)
・木造建築の体験がない世代が世の中の中心に
・かつてはコンクリート住宅(不燃住宅)は木造住宅のワンランク上の存在だった
・森林から工務店・建築家・住まい手まで一緒になってつくるチームづくりが良い住まいづくりの秘訣
とても勉強になったフォーラムでした。
 9/10に正式にオープンする「木想館」に行ってきました。
9/10に正式にオープンする「木想館」に行ってきました。
-木を想う家づくり-というコンセプトでつくられています。
 まずはFurniture Studio かぐら
まずはFurniture Studio かぐら
家具づくりからスタートした工務店とのこと。
様々な地域から取り寄せた国産材を使った家具がおかれています。
思わず使ってみたくなるような家具がおかれています。
 こちらは阿蘇小国の家。
こちらは阿蘇小国の家。
熊本の小国の森から切り出された材木を使って建てられた住まいです。
こうした森林と都市の良い関係が家づくりの中で育まれると良いですね。
ちなみに雨といも全て金属製。
こだわりを感じずにはいられませんね。
(残念ながら某社の製品でした)
 最後は東濃ひのきの家。
最後は東濃ひのきの家。
良質な木材産地の工務店のモデルハウスです。
木をふんだんに使った気持ちの良い住まいでした。
そしてこのプレオープンイベントには、350名の方が来場されたようです。
山の方から工務店・建築家・建材メーカーそして住まい手まで。
木を愛する方々がその大半だったように思います。
たまたまある学校でこんな話が出ました。
既存の学校の夏対策の一環として考えているようです。
簡単にいくものなのでしょうか???
 お世話になっている栗原先生の手掛けた建物の見学会に行って来ました。
お世話になっている栗原先生の手掛けた建物の見学会に行って来ました。
この写真のネットは「緑のカーテン」をつくるためのもので、ネットの上部から雨水が流せるようになっています。
中央の横パイプのすぐ下についているのは雨とい。散水した雨をこちらで改修します。
ちなみに屋根散水も出来るようになっていて、雨といで集めた雨は雨水タンクを経て、また散水される循環が出来ています。
来年の夏が楽しみです。
 (社)東京建築士会の平成17年度住宅建築賞、
(社)東京建築士会の平成17年度住宅建築賞、
入賞作品展をみてきました。
既にブログにもUPしている廣部剛司先生の受賞作品を見に行くためです。
同じ奨励賞に以前から面識のある井口浩先生も受賞されていました。
何とも偶然な出来事でした。
↑茶畑の家(廣部先生)
↓ハウスフォレストリー幸手(井口先生)
さて、我々としてはどのような協力ができるのでしょうか?
この町に暮らす・・・「住む」05年夏号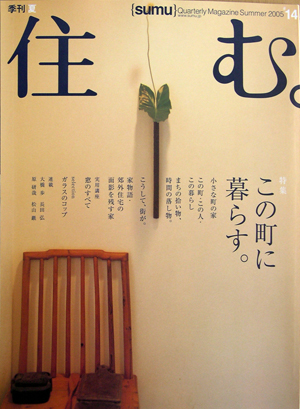
今回の「住む。」はまさに伊礼先生の特集号ですね。
特に「窓のすべて」は楽しく読ませていただきました。
今のサッシはすべて閉めたときの快適性を競っているように感じます。
窓はやはり開けたときの快適性も競うようにならないといけませんね。
風は入るが、虫は入らない とか。
安心して開けられる とか。
窓を開けると座れる とか。
昔の肘かけ木製サッシの窓枠は、座りやすかったですね。