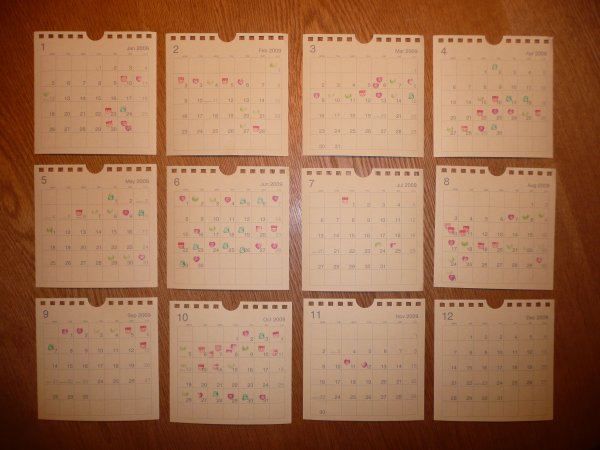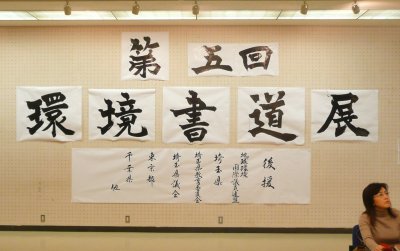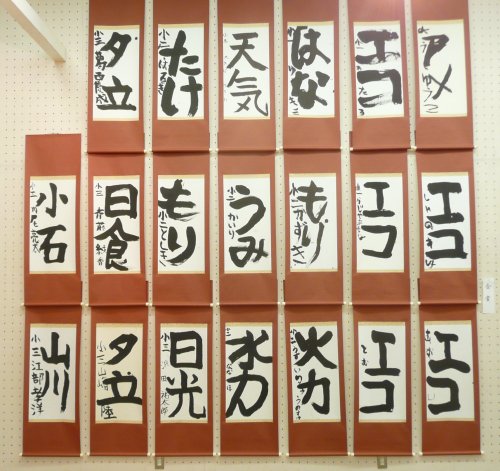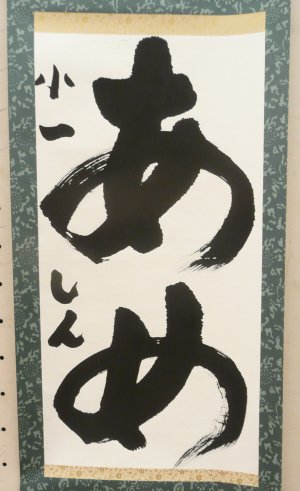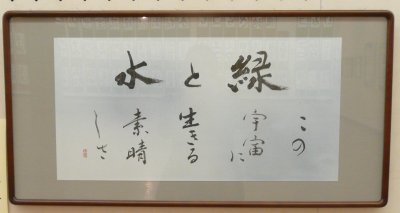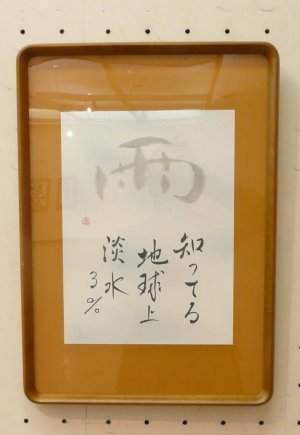トイレを雨水で流した日にマークがついています。
1月- 7日間(満水1回)
2月-10日間
3月-10日間(満水1回)
4月-14日間
5月-10日間
6月-22日間
7月- 3日間
8月-16日間(満水3回)
9月- 8日間
10月-20日間(満水2回)
11月- 2日間
12月- 0日間 2009年 122日間/365日 33.4%
満水とは、1tの雨水タンクが一杯になってしまっている状態。
2008年比べると、利用日数が減っています。 (08年 198日)
ちょっと残念な結果に終わってしまいました。
いよいよあと10数時間で2010年。
来年も雨のみちをデザインする仕事に徹していきます。
ご支援よろしくお願いいたします。