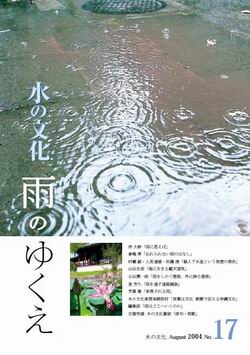8/1 私の所属する FCキャンプ に参加してきました。
「障害」を持つ人も持たない人も
共に同じように生きる社会(共生社会)を築き上げることを目指して行われています。
肢体不自由児と健常児が一緒に過ごす4泊5日のキャンプです。
山中湖で行われました。
当日は薄曇り程度の天候。
湖で乗るビックカヌーのお手伝いで、
何かあったときのための手こぎ監視ボートに乗りました。
肢体不自由児と健常児が助け合いながら一緒に生活する姿はとても気持ちの良いものです。
今年が30回目。
こうしたご時世で資金集めも大変なようですが、こうした取り組みは是非継続させたいです。
昨年からある企業がこのキャンプのお手伝いに社員を数名派遣されています。
研修というと机上で行われるケースも多いですが、
体験から学ぶことの方が、その後の考え方や行動に良い影響を与えると思います。
ちなみに私は2時間のボートに乗っただけで、太股・すねがひどい日焼けになりました。
ずっと座っているため太陽光をまともに受けてしまったようです。
HP もあります。是非ご覧ください。