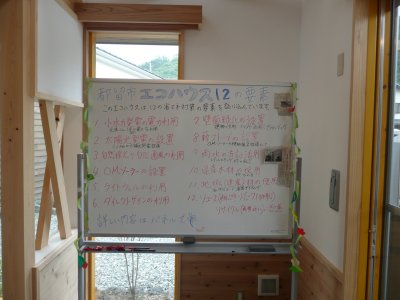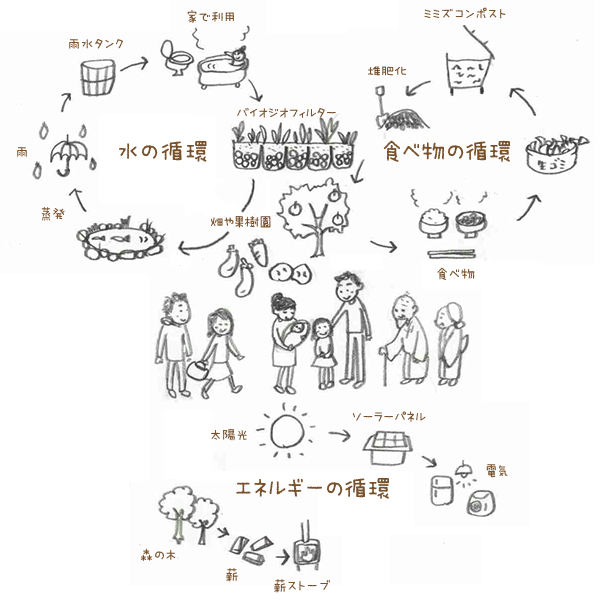先日、IDEEの自由が丘店を訪ねたとき、
オットマンの相談をしたところ、
・コンパクトラウンジソファは残念ながら廃番
・この茶色い生地も廃番
但し、まだ生地は残っているので特注で対応可能だろうとのこと。
早速特注で注文したオットマンが先日届きました。
せっかくの機会ということで、
IDEEの方が3名、納品を兼ねて自宅までお越しになりました。
*既に3年も経過し、だいぶ雰囲気も変わりましたが・・・
それではということでそのまま宴会に。
楽しいひとときを過ごすことができました。
 ちょっと大きいかなあとも思いましたが、
ちょっと大きいかなあとも思いましたが、
実際には、家族で取り合いになっています。
充分な大きさがある分、独り占めすることなく、使わせていただいています。
「提供した商品が実際に使われている場面に立ち会えるのは嬉しい」
子どもたちが使っている様子を見て感じたIDEEの方の言葉。
売りっぱなしになりがちなメーカーにとってこうした機会は大切なんですね。
仕事があるということで一人の方は早めにお帰りになりましたが、
結局、ビールを皮切りに、赤ワイン3本、秩父で購入した無濾過原酒純米酒1本(4合)。
店舗のデザインやリフォームなど最近の取り組みについて伺うことができました。
*会社としてお役に立てる話は少なそうですが・・・
ちなみに廃番になってしまったコンパクトラウンジソファ。
特注であれば対応できるとのことです。