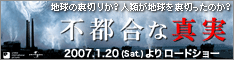「雨漏りトラブルの現状と対策」というNPOの講義に参加した方からの話でした。
雨漏り診断の考え方と原則
・先ず、先入観を捨て去ること(心構え)
・5つの原則
①現状を正確に把握する。(構造・工法・環境・経年)
②問診を徹底する(雨漏り状況を聞く・いつから・場所)
③仮説をたてる (もし~ここから・こうなる・多くの仮設)
④冷静に観察する(施工の状態・シーリングの劣化状態など)
⑤雨水は上から下に流れる(雨漏りの迷路に迷ったら、考え方をシンプルに戻す)
一般的に雨漏りはその原因がつかみにくいケースが多いようです。
雨のみちがうまくデザインされていないと、こうした雨漏りにつながるケースも出てきます。
また上記にあるように、先入観を捨てて考えることが大切なようです。
雨仕舞いを大切に考える。
最近ではコーキングで処理するケースも増えてきていますが、
雨仕舞いは板金業の大切な役割でした。
建て替えサイクルが短い場合は良いかもしれませんが、
欧米並みに日本の住宅の建替年数も長くなっていくことを考えると、
コーキングだけに頼るのではなく、昔ながらの雨仕舞いの視点や技術が
求められてくると思います。
雨のみちをデザインする仕事において、雨仕舞いは大切な視点。
結果として、雨から住まい手の生活が長期間にわたり、守られることになります。
雨に対抗するのではなく、雨とうまく付き合っていく感覚が必要なのではないでしょうか。