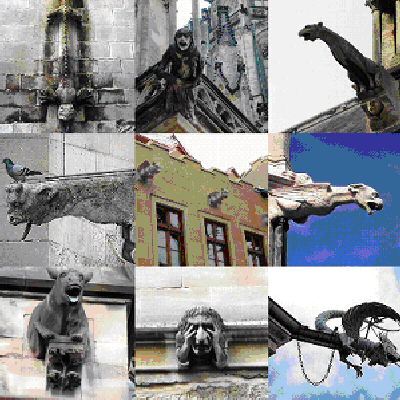レーザー導入(1126)
「ガーゴイル」ってご存知ですか? そんな一言から朝会がスタート。
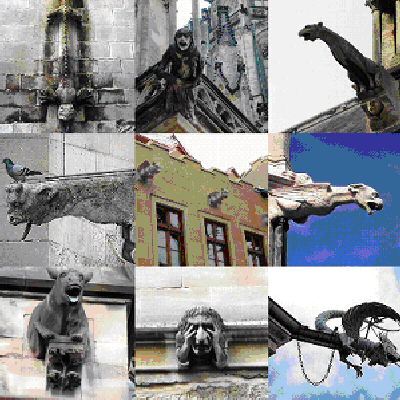 ノートルダム寺院のような中世期のゴッシック建築などの屋根部に見られる、
ノートルダム寺院のような中世期のゴッシック建築などの屋根部に見られる、
魔物の姿をした彫刻物が突き出している部分。
(ジャガーのエンブレムのような。。。)
これは屋根などに降った雨が、この魔物の口などから吐き出されるという具合に、
建物から遠くへ排出するためのものだそうです。
ガーゴイルという言葉そのものは「屋根から水を流しだす」という意味合いとして
広義的に使われるようです。
そして、建物から遠くへ排出することで、外壁などの石と石の間の漆喰(?)などを
守る意味でも重要な役割を果たしているそうです。
建物を守るという意味では、今でいう「雨仕舞い」なんだなぁ~と思いました。
また当時は宗教的な意味合いが強くラッピングされていて、
魔物の口から流れ出す水が、「外に祓い出される悪霊」を象徴し、
またそれ自体が悪霊の進入を防ぐ(寄せ付けない)とした、
日本でいう「鬼瓦」のような意味合いもあるそうです。
現在でも、雨が降るとこのガーゴイルから雨水が流れ落ちるそうです。
現地ではこの流れ落ちてくる雨を「悪霊の水」という迷信的な認識もまだあるようで、
なるべく被らないようにしているそうです。
ちなみにエジプトでもこうしたガーゴイルというものが存在していて、
当時は流れてきた雨水で聖杯などを洗うなど、「雨水利用」なるものが行われていたようです。
ヨーロッパに行った際にガーゴイルを見たことは何度かあります。
ただ残念なことに雨の日に見た経験はありません。
おそらく雨の日だったらガーゴイルから出てくる雨の下に行って
「悪魔の水」をかぶっていたかもしれません(笑)。
雨といの大きさを考えるとき、その地域の降雨強度を考えながら
といの大きさや形状を加味して、提案する事があります。
つくり手からの要望の中は、
・あまり大きなものをつけたくない
・100mmくらいの豪雨の時は溢れても一緒
そんな意見を伺うこともあります。
当社が考える雨のみちはどこからでもバシャバシャと雨が溢れるのではなく、
たとえば、一定量を超えたときの溢れる場所までデザインすることだと思います。
ガーゴイルのように、建物や隣地や庭に外のないようなところに雨があふれ出す。
リビングからその溢れる様子を見ながら、
「あそこから雨が出ているということはかなりの豪雨だなあ」と実感できる。
そんな雨のみちもおもしろそうですね。