なかなか綺麗な風景です。
11月末にお邪魔するときはどんな風景になっているのでしょうか?

日々心動かされたことを記していきます
もう7年も前の話ですが、ちょうど会社にある資料を整理していたところ
98年に墨田区で開催された
雨水利用自治体・市民フォーラム「21世紀の雨水利用を展望する」
の報告書が出てきました。
何とその時、伊礼先生とお会いしていた事実が判明しました。
97年に雨水フェアin沖縄が開催され、中村家などを見てきた翌年。
男同士で赤い糸はありませんが(笑)・・・・。何か運命を感じています。
お客さまをお連れして産業技術記念館に行ってきました。
別名「トヨタテクノミュージアム」。
トヨタという企業の技術的進歩、歴史についての記念館です。
まずは織機関係。 手づくりの時代からどのようにして機械化されていったかがわかります。
手づくりの時代からどのようにして機械化されていったかがわかります。
皆さん真剣な眼差しで見学されていました。
ちなみに織機関係の機械で得たお金が自動車開発に活かされていることもわかりました。
そして自動車関係。 金属が関係することもあってこちらも興味津々。
金属が関係することもあってこちらも興味津々。
アッという間の2時間でした。
ちなみにこの写真は市販一号車。
エンブレムが漢字になっていますね。
ちなみに当初は「トヨダ」だったそうですが、
濁点が気になることと「トヨタ」にすると8画で末広がりということで
その後、「トヨタ」に変わったとのこと。
どこかの会社と同じですね。
11/11までの4日間。
どのような出会いがあるのか。楽しみです。
また同会場内の各所で様々な講演会が開催されます。
ちょっと気になるモノをピックアップしてみました。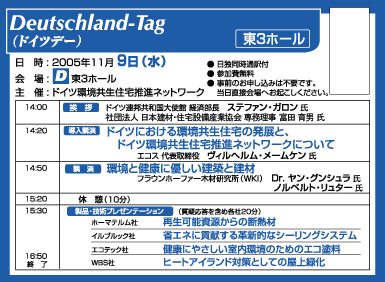 メームケン氏には以前、ドイツでお会いしました。
メームケン氏には以前、ドイツでお会いしました。
その際には、現地の雨水利用施設をいろいろ見学させていただきました。
奥様が日本人なんですね。親日派の方です。
11月10日(木)
12:00~12:50
「学校発エコ改修事業について」
善養寺 幸子氏 オーガニックテーブル株式会社 代表取締役社長
学校発の地域環境教育により、教育界・建築界・自治体を変える
三位一体の環境改革を推進するための方策について講演します。
足立区の学校でエコ改修を行い、
環境省と組んで、全国規模で進めています。
今年の夏、善養寺さんの手掛けた完成現場見学会にも行ってきました。
雨水利用についてもいろいろトライされている方です。
11月11日(金)
13:00~14:30
「無印良品の家づくり」
土谷 貞雄氏 ムジネット株式会社 住空間事業部長
土谷さんも知り合いです。
有楽町と世田谷の無印良品の家は見に行きました。
モデルハウスも各所に広がっているようです。
一部のモデルではガルバの雨といも採用になったようです。