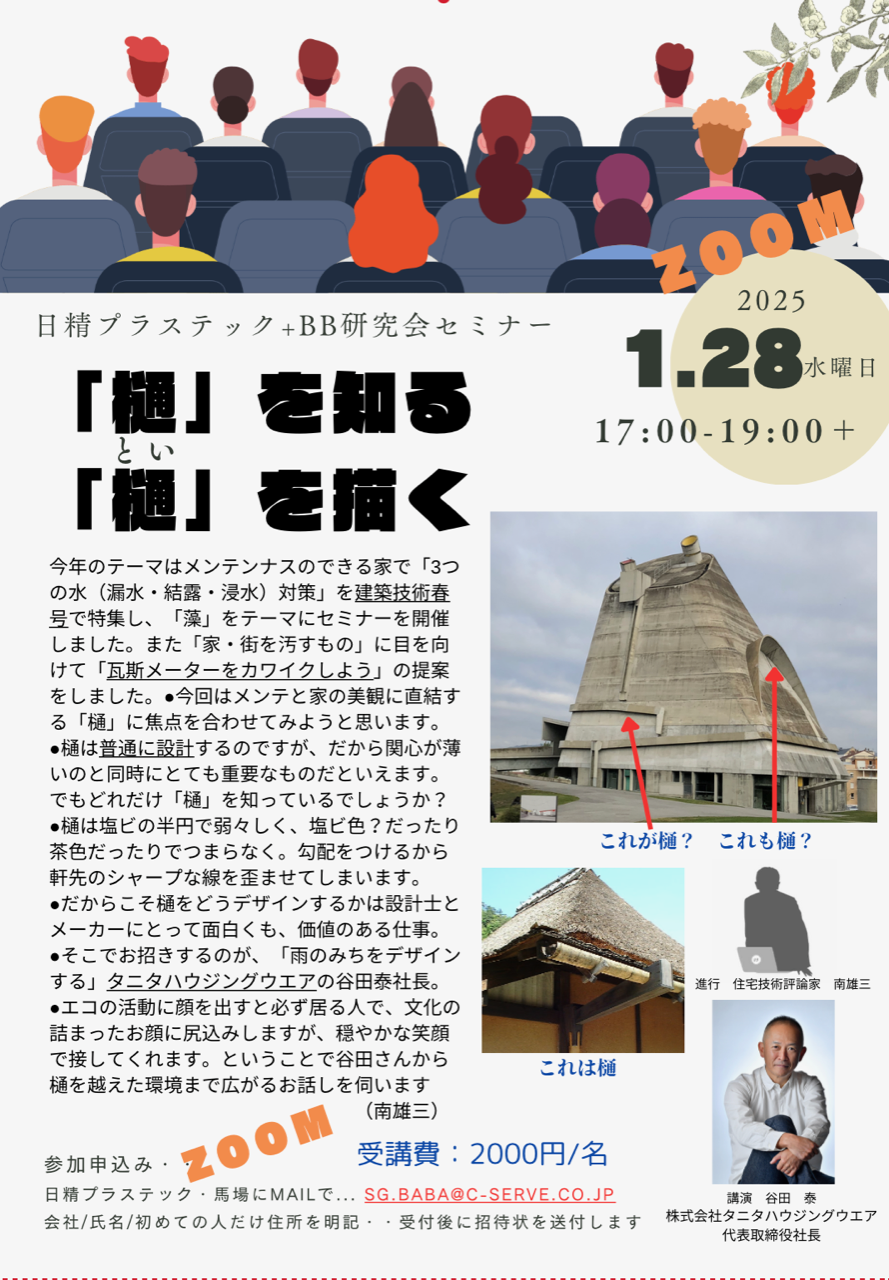
屋根コン授賞式も無事?終了し
いよいよ明後日1/28(水)17:00~
「樋」を知る「樋」を描く セミナーが
リモート開催されます
既に50名近くの方にお申し込みいただいているようです
みなさんにお配りするレジメはこちら
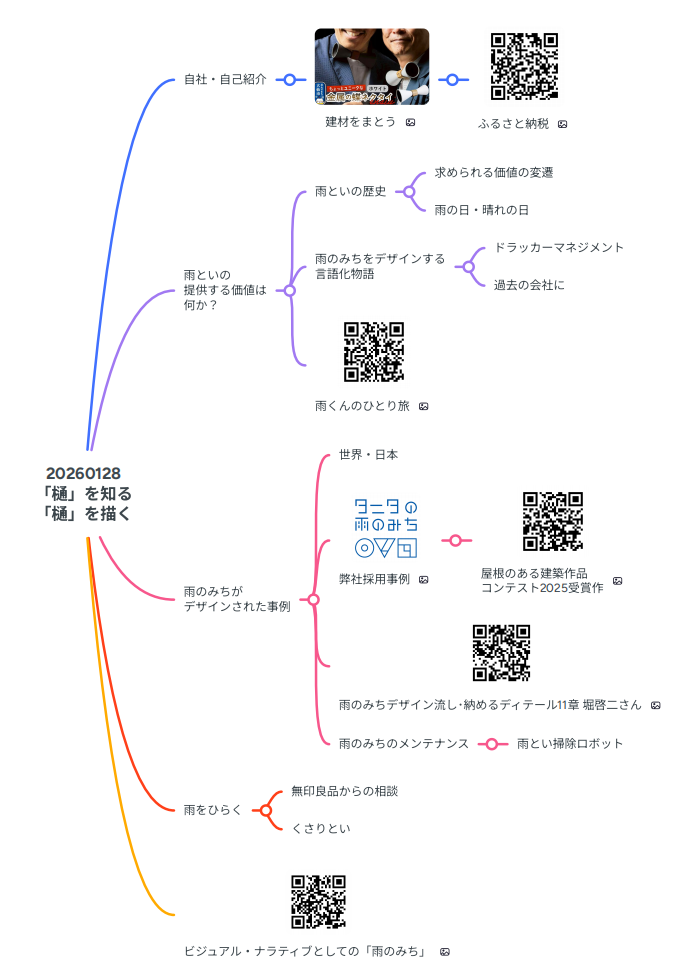
前半の南雄三さんのお話のあと
私のパートではこのレジメを中心に45分程度お話する予定です
*まだ多少変更になるかもしれません
リモートなのでどこまで皆さんの反応をいただけるかはわかりませんが
セミナー中にコメントなどもいただけると嬉しいです
*スマホとPC両方で入ったほうがやりやすいのかな?
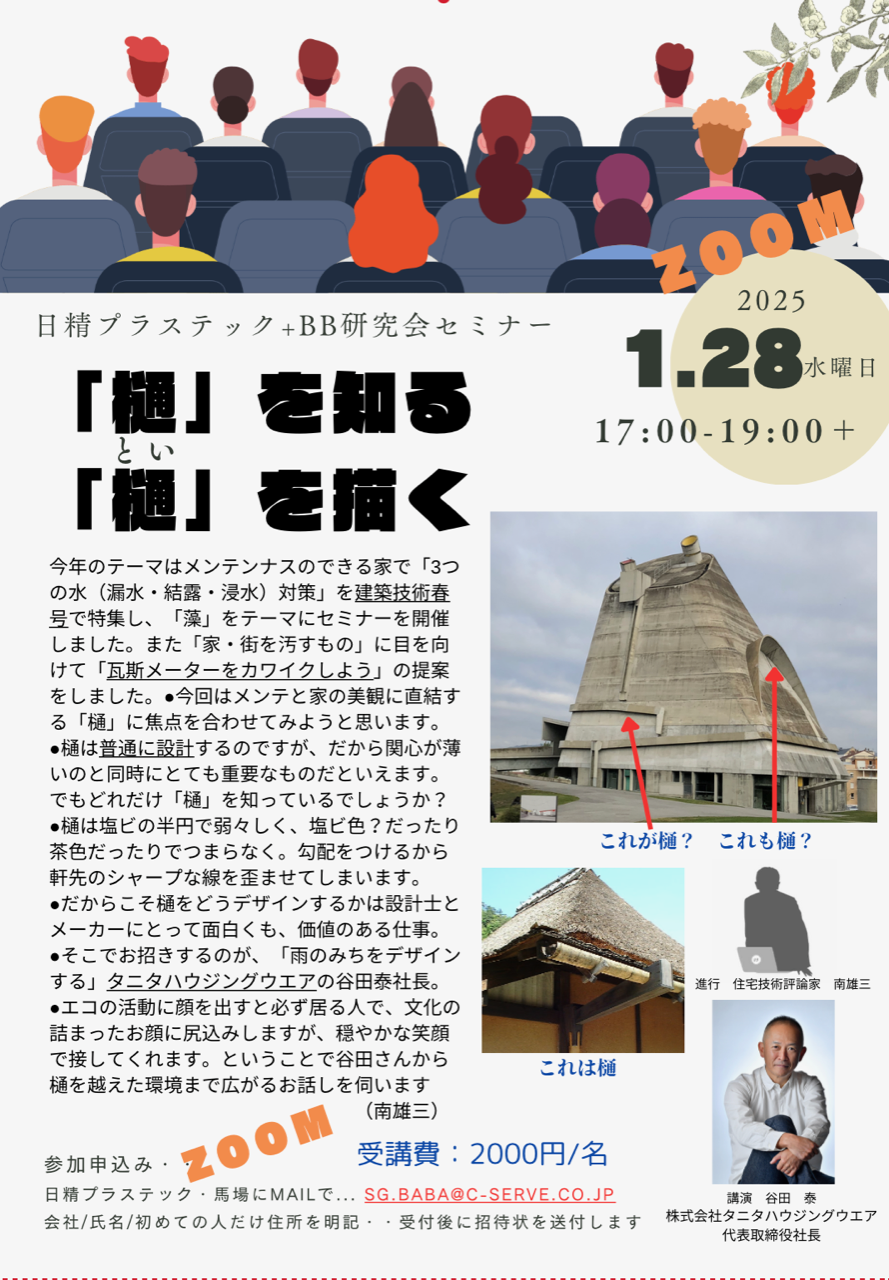
このフライヤーをいただいた時
サンピエール教会や竹の雨といは
私が講演する際に必ず使う写真なんです
*受講料は無料となっています
何の打合せもなくこうしたところに共通点があるのも嬉しい
樋というより「とい」や雨のみちのお話がメインになってしまいそうです
せっかくなので1月24日(土)に行われた屋根コン2025授賞式のお話も
すこしできたらと思っています

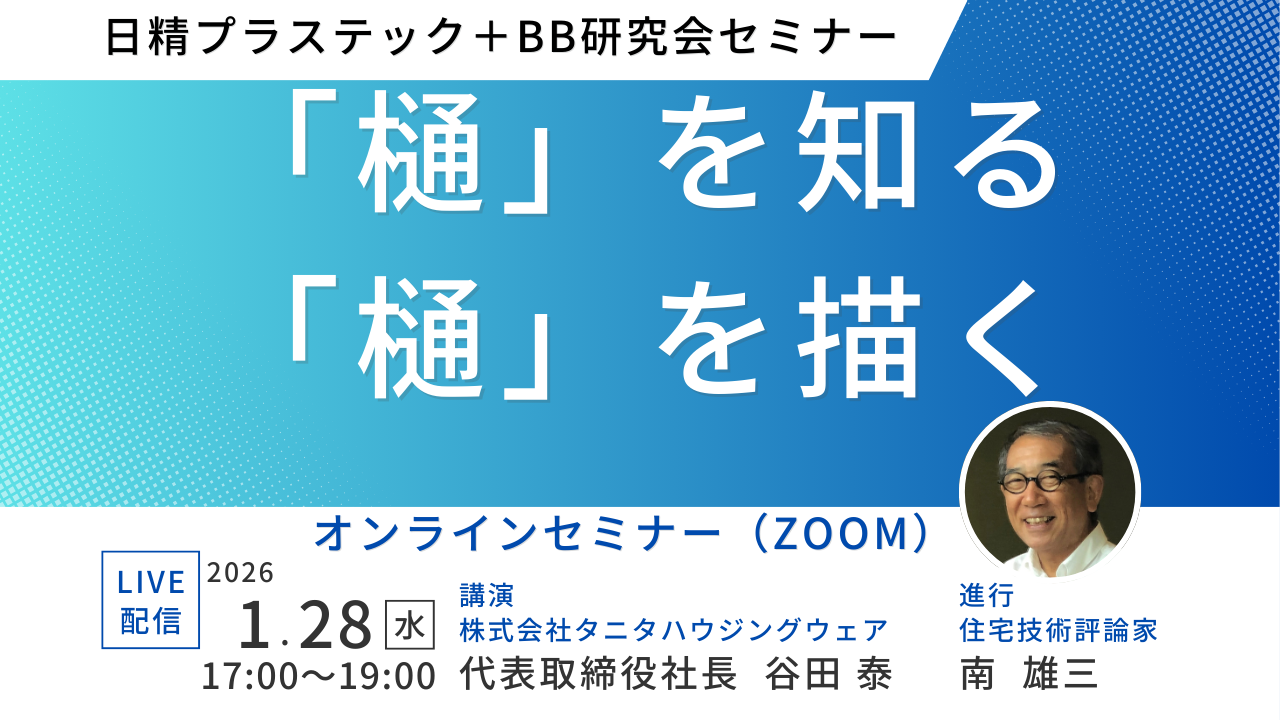

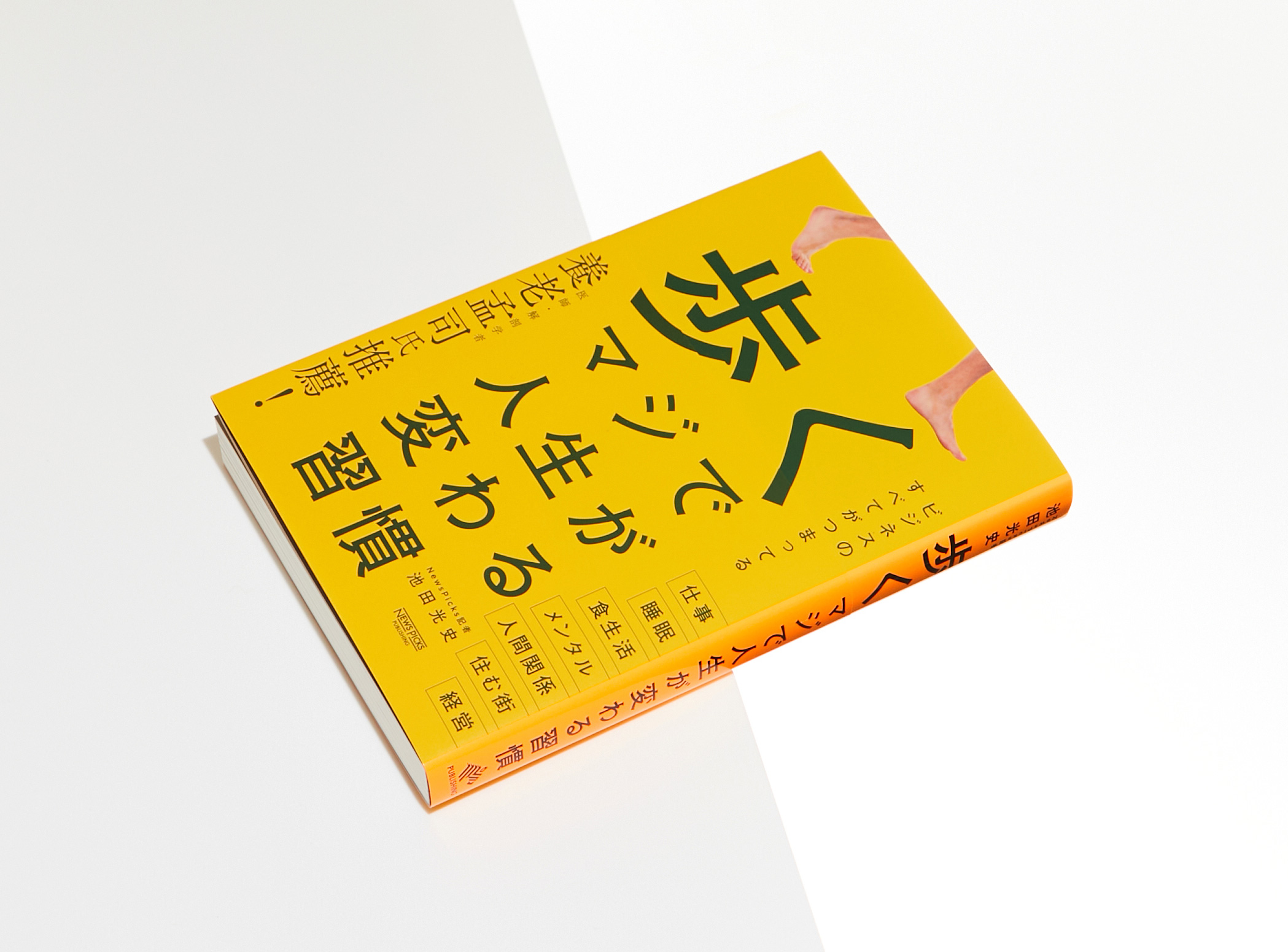

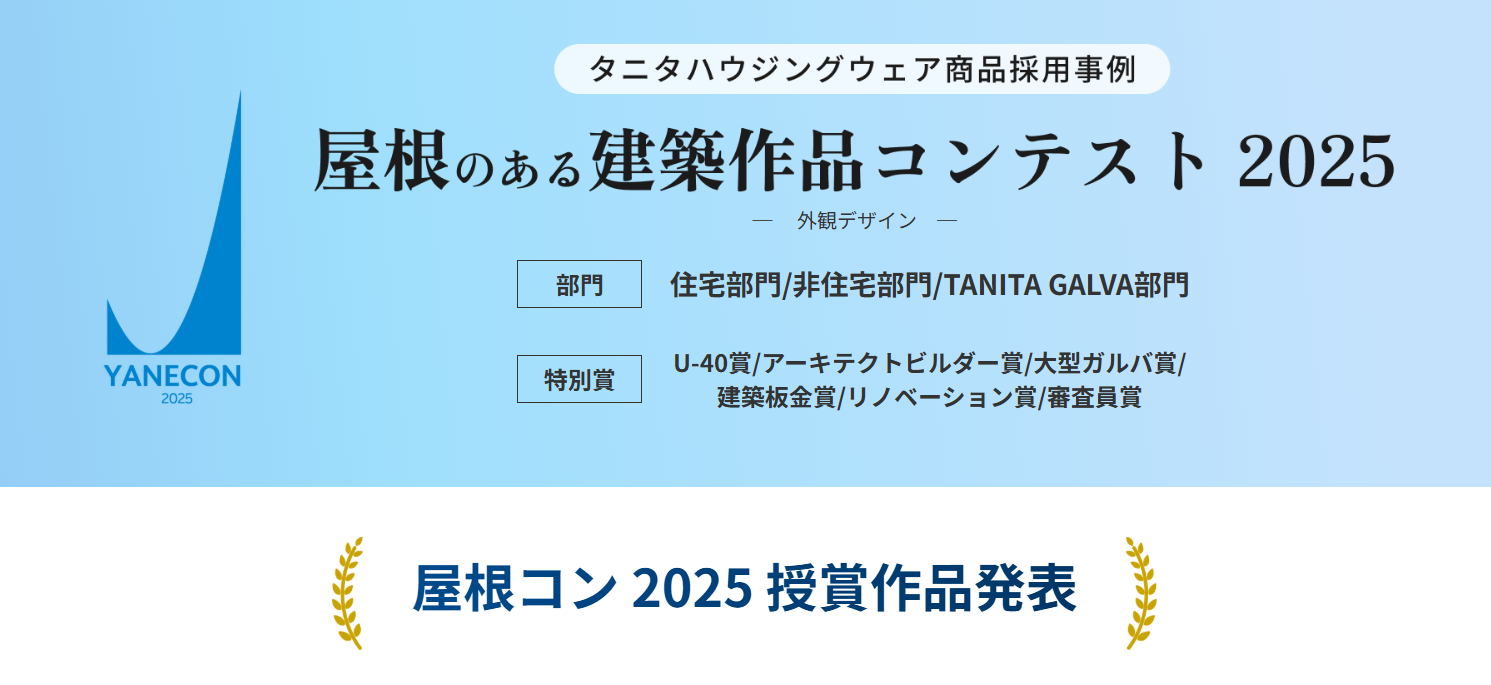
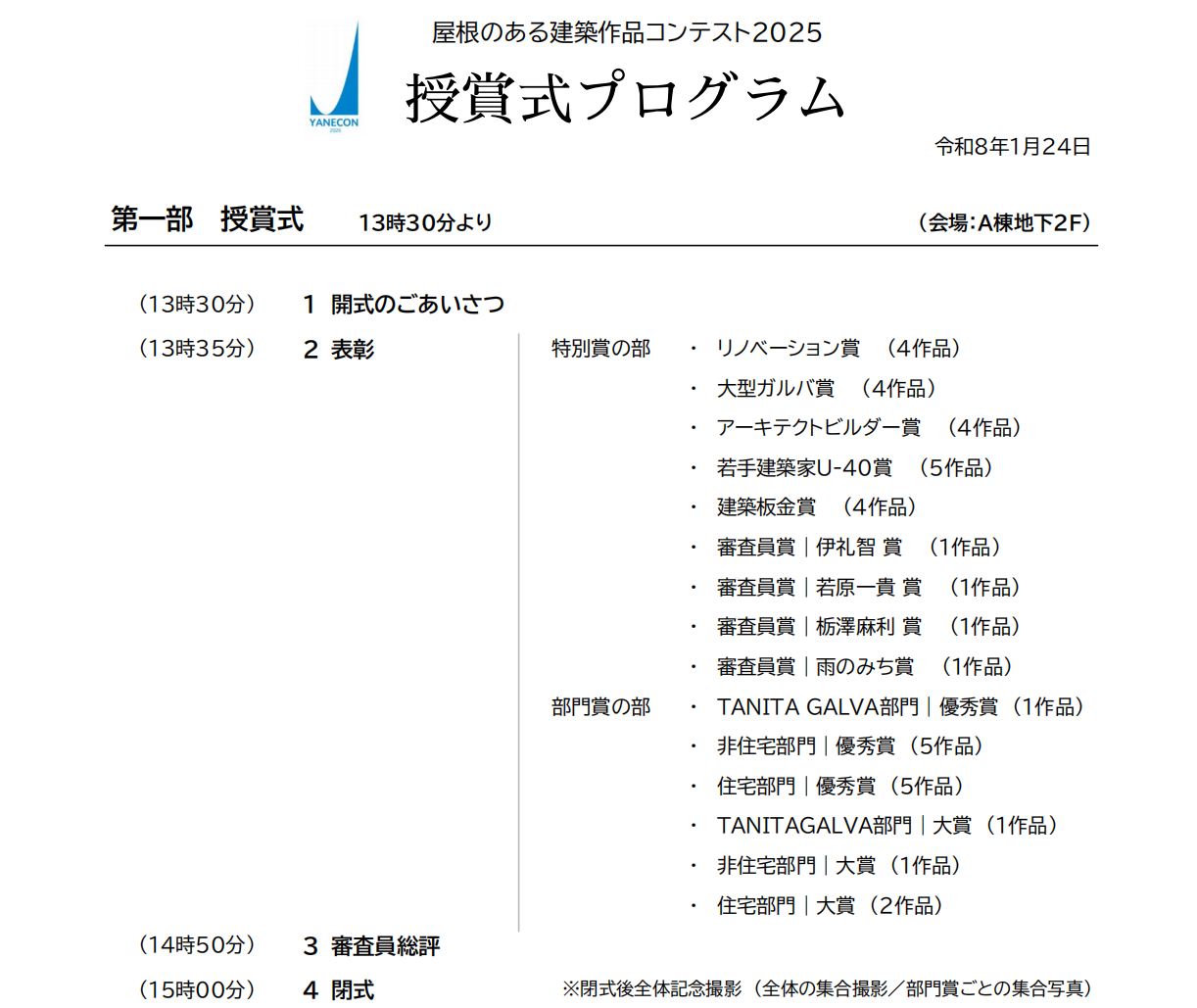






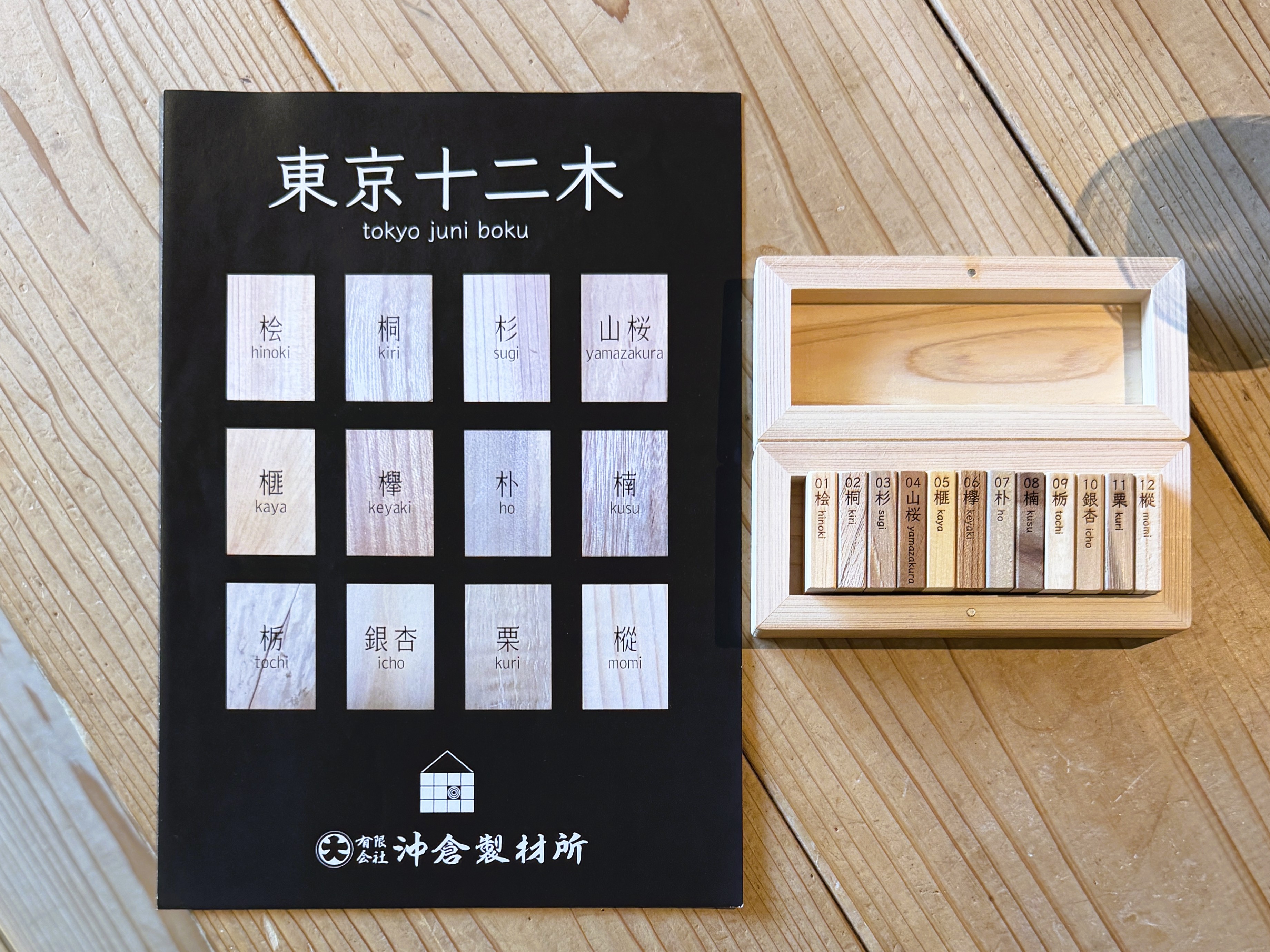

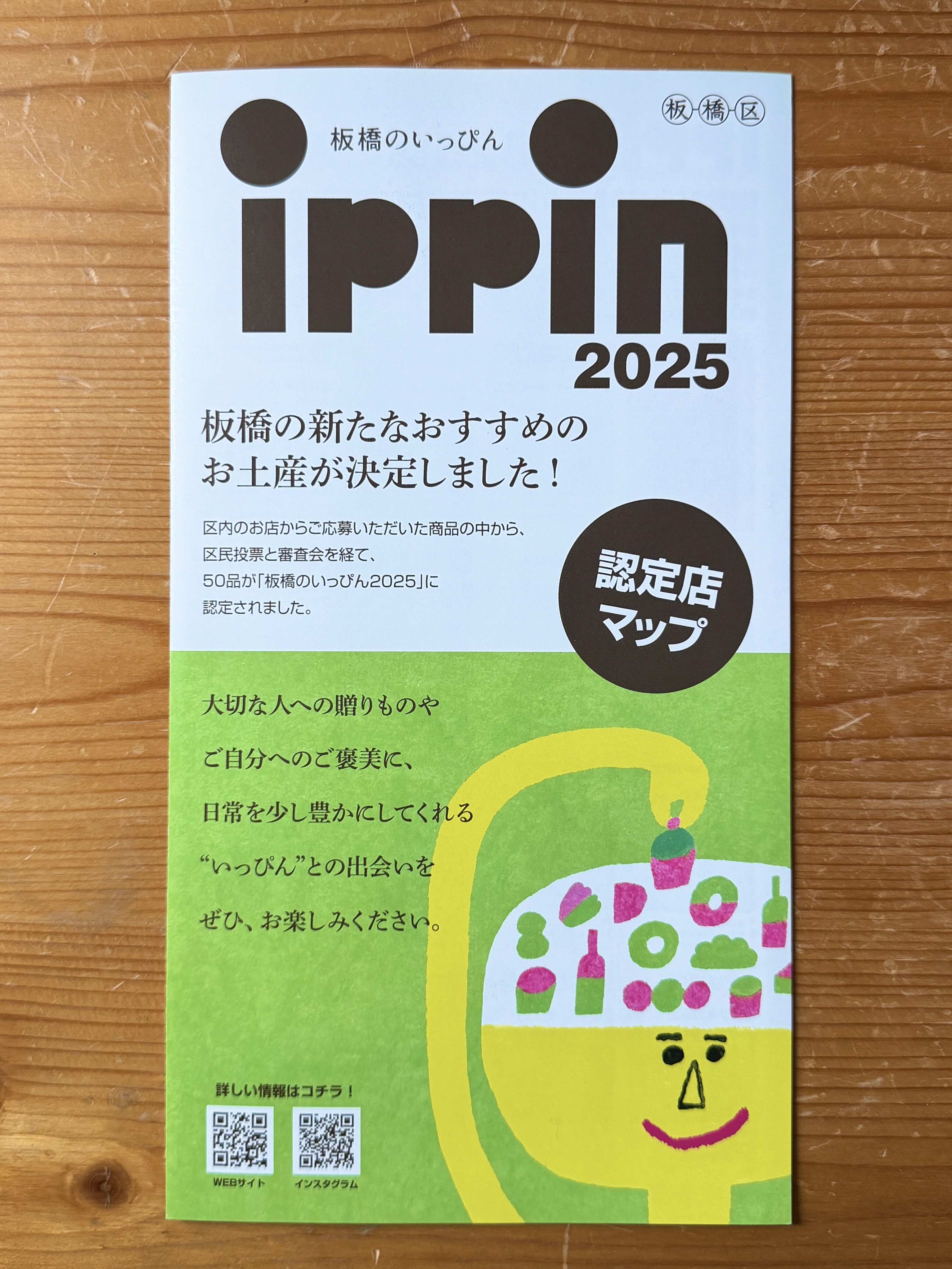



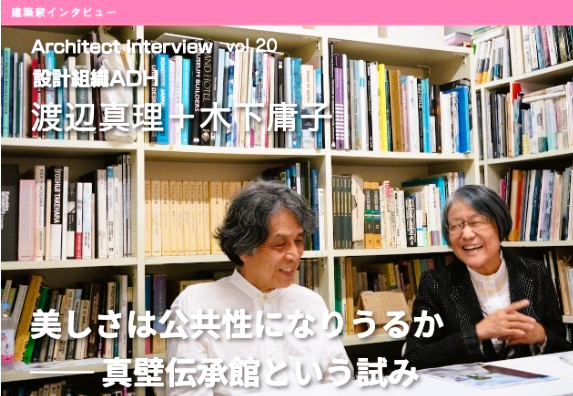

 昨日、
昨日、

























