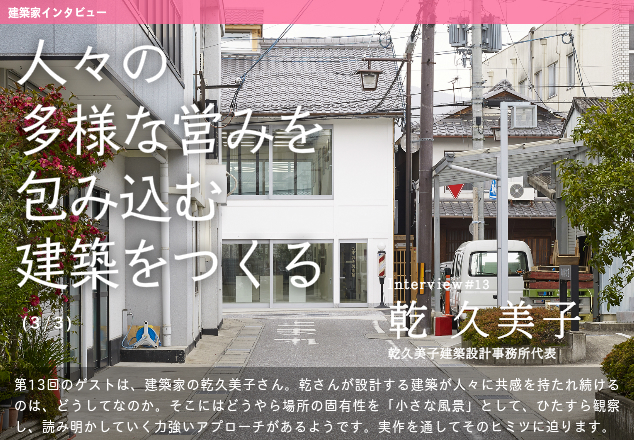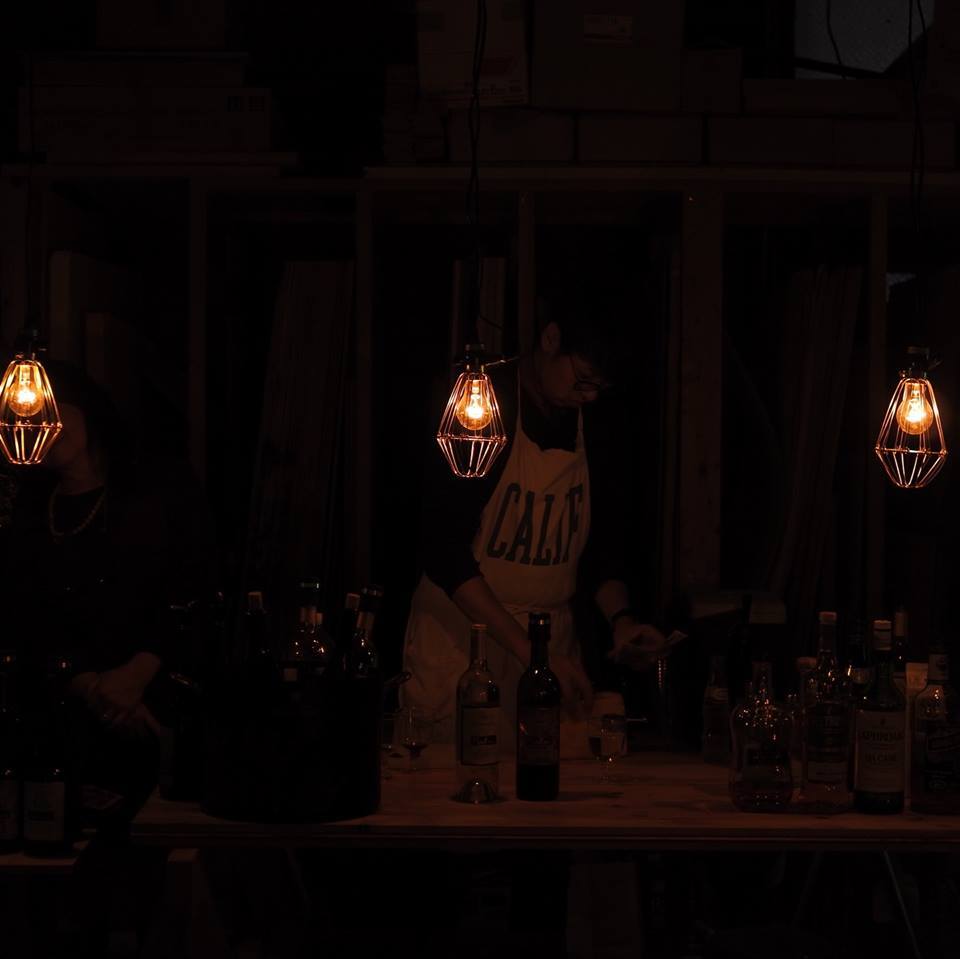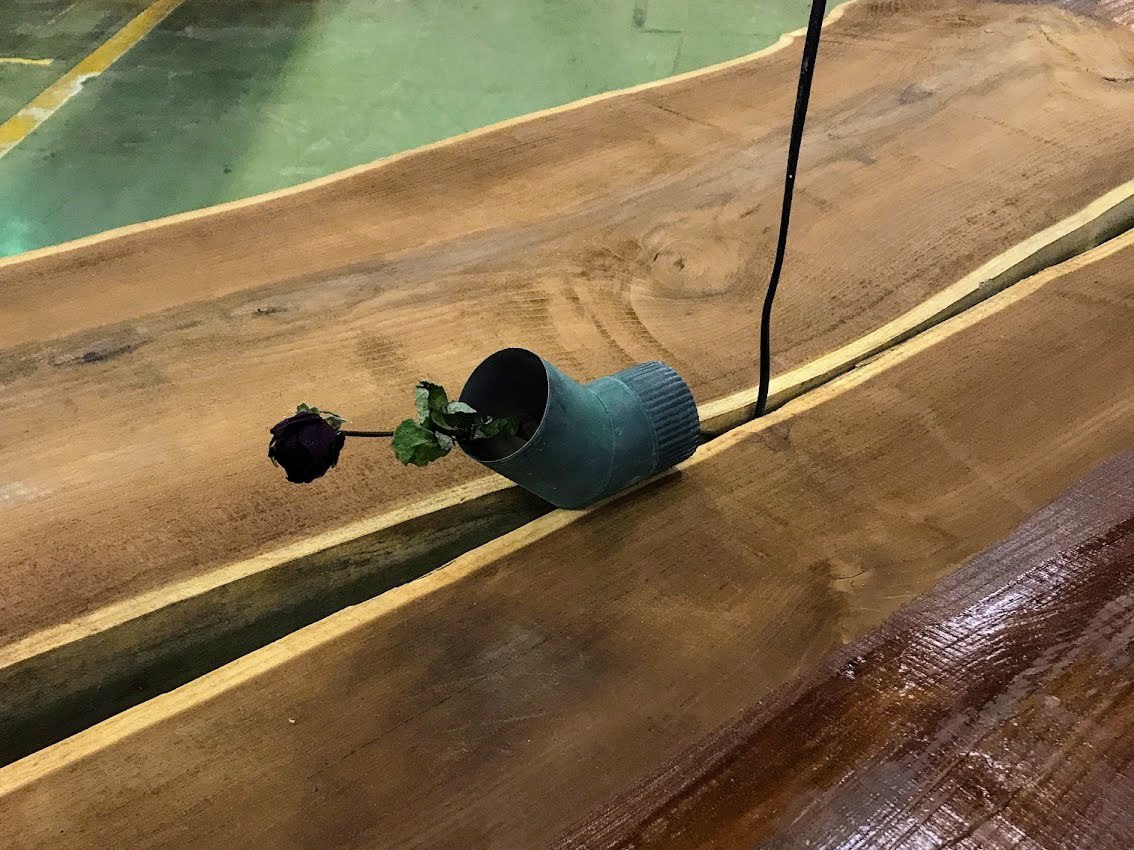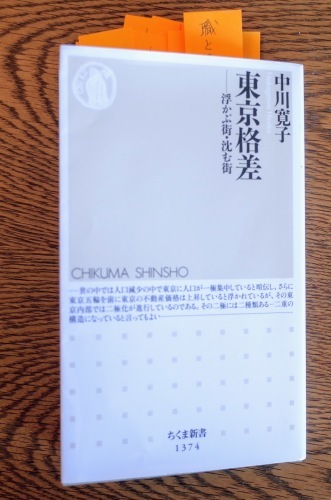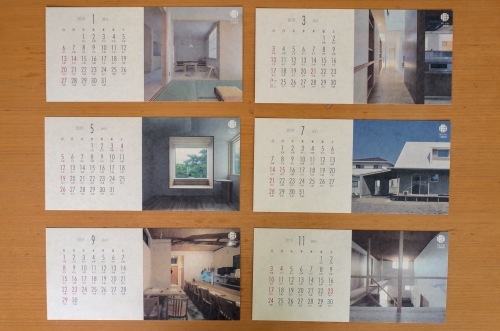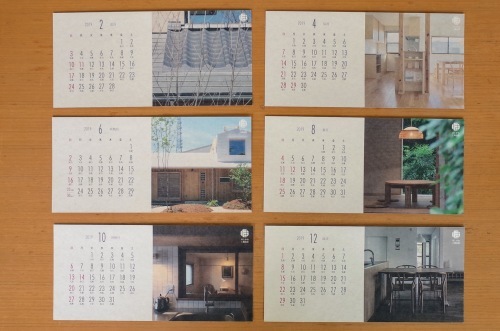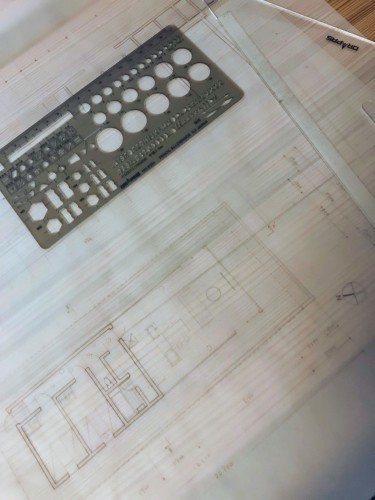12月24日、弘明寺の家(マンションリノベーション)を見学させていただきました
12月24日、弘明寺の家(マンションリノベーション)を見学させていただきました
こちらは茶の間兼寝室
既存の出窓を利用し、縁側のような雰囲気に仕上がっています
 角度を変えて、夕暮れ時です
角度を変えて、夕暮れ時です茶の間は段差があり、腰掛けることもできます
左手には無印良品のプラケースを利用した飾り棚
キレイに納まっています
 ダイニングからキッチンをみたところ
ダイニングからキッチンをみたところ
裏動線が確保されていて、洗面、浴室へとつながっています
その後は近所の居酒屋で会食
イブの夜にもかかわらず、女子を含め、多くの方が集まっていました
小谷さん、お忙しい中、ありがとうございます