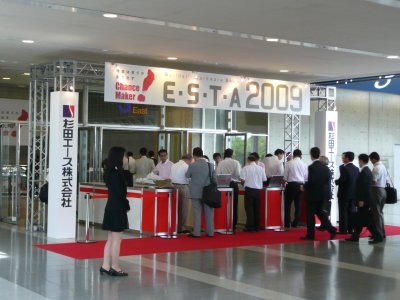7月に入りました。既に今年も後半です。
月日が経つのが早く感じられる年齢になってきました(笑)。
さて、表記にもあるとおり
リフォーム産業フェア09+工務店フェア09 に出展いたします。
予算緊縮の中での出展なのでグループ企業の 吉岡 と一緒に出展します。
日時 7月14~15日 10:00~17:00(両日)
場所 東京ビックサイト 東1ホール
多くのお客さまのご来場をお待ち申し上げております。
この展示会の特徴はなんといってもこの2日間で100回以上開催されるセミナー
詳細は こちら
7月15日には下記トークショーも開催されます。
一歩先行く建築家トークショー『小さな家』伊礼智×『町家』趙海光 変わる住宅設計トレンド
建築家伊礼 智 氏 × 建築家趙 海光 氏 × 聞き手小池一三 氏
なおどのセミナーも席の予約はできず、先着順になるとのこと。
参加される方はお早めにお越し下さい。
セミナーは参加料がかかるように説明を聴いていましたが、
HPからはよく判りませんでした。
出展企業ということでこんなものも頂いています。 ご希望の方はお早めにお申し出下さい。
ご希望の方はお早めにお申し出下さい。