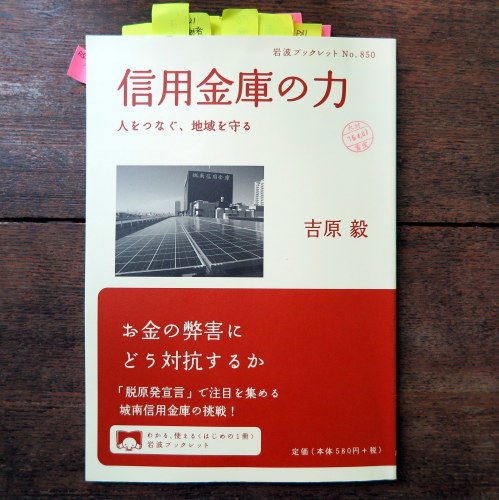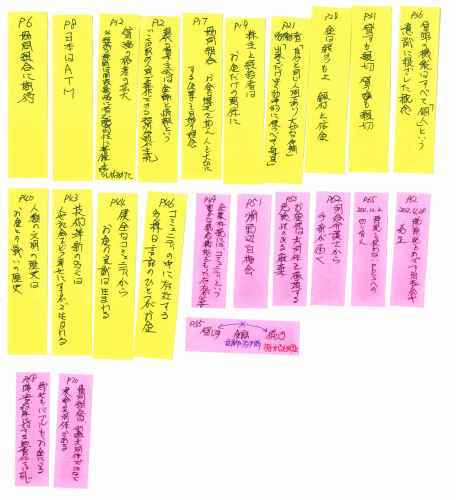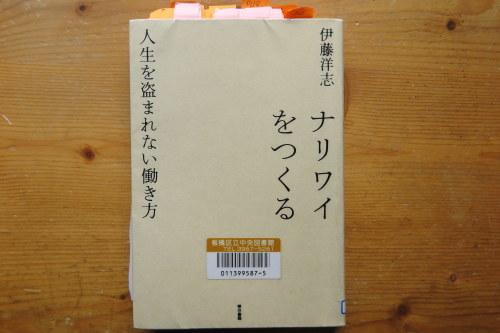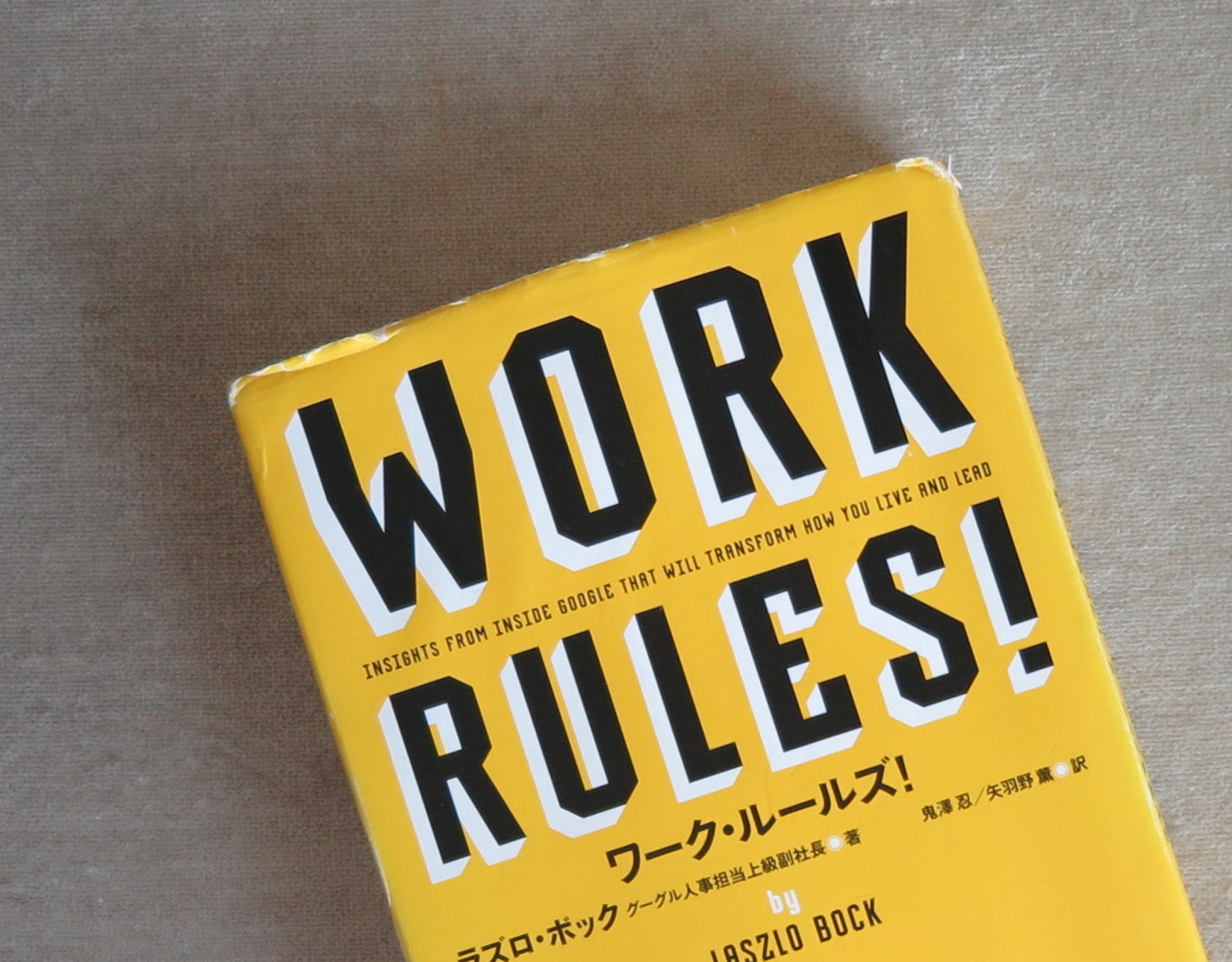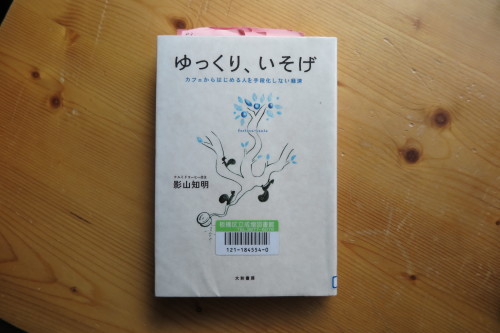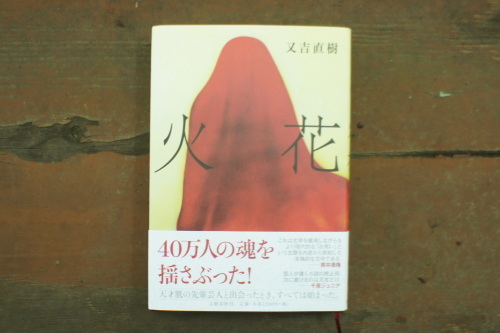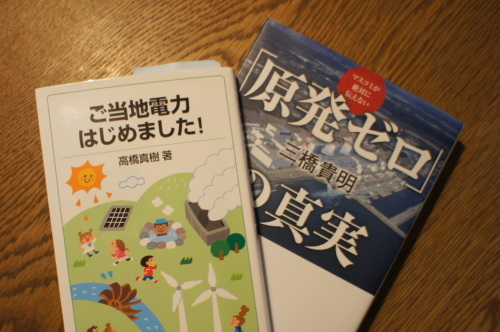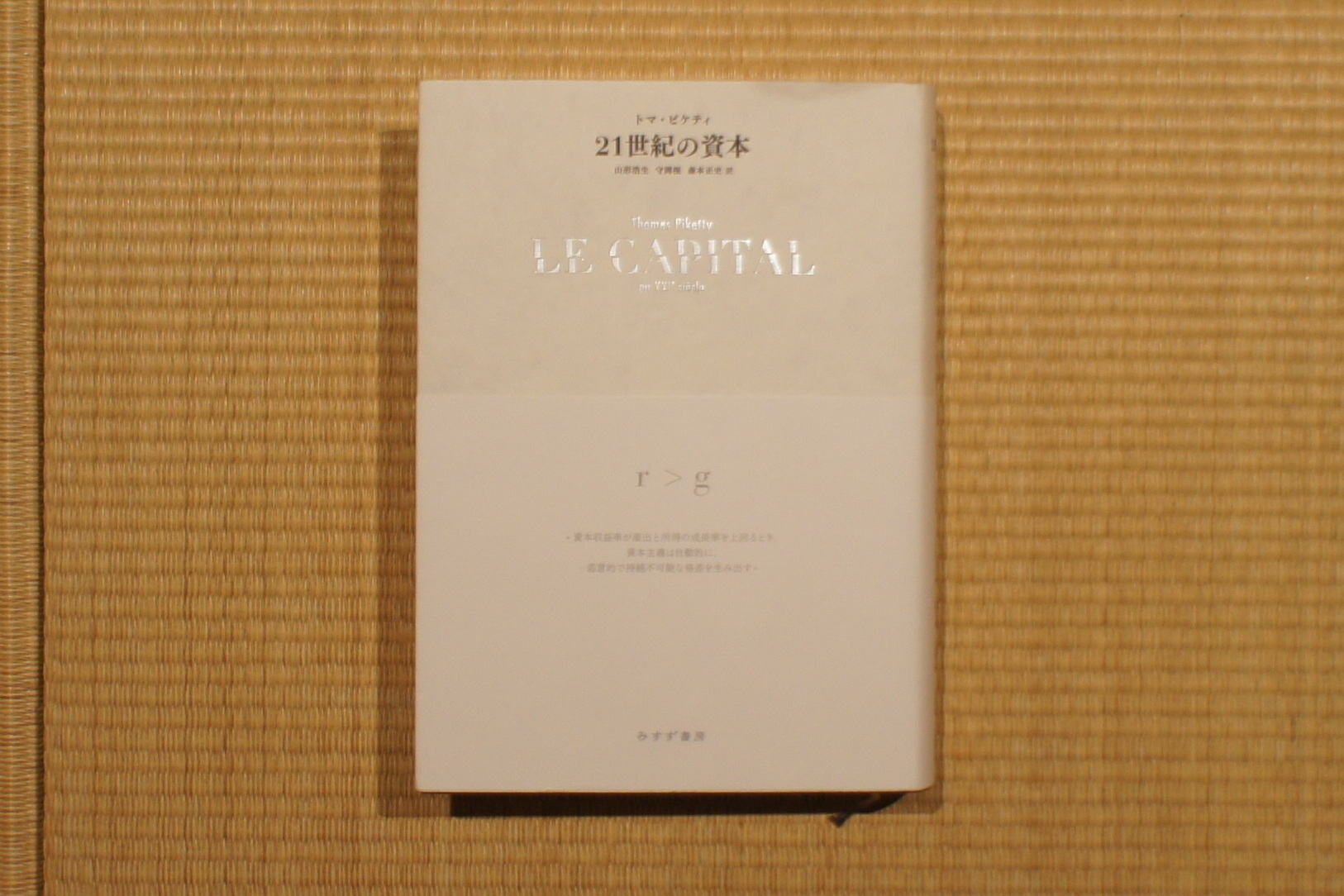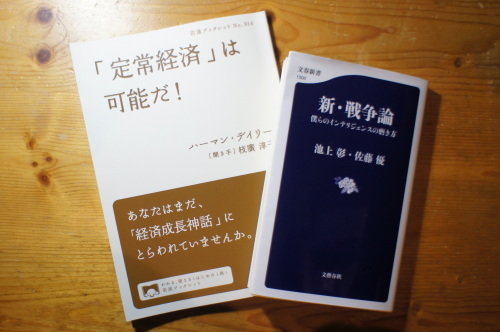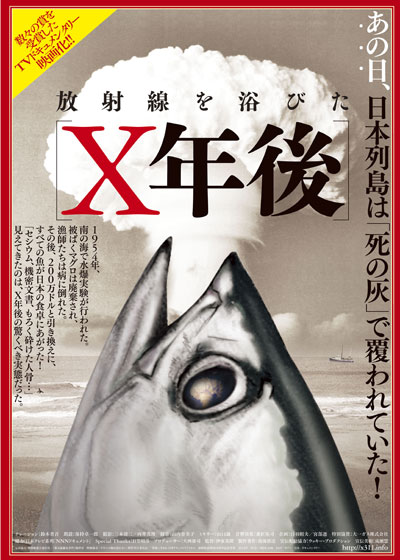お金の弊害にどう対抗するか
ナリワイをつくる
WORK RULES!
今後の経営の考え方に活かしていきたいと思います。
ゆっくり、いそげ
火花
上映会を見据えて
映画「日本と原発」の上映会を前に、いろいろ考えてみたいと思っています。
私たちがいかに大切なことを他人任せにしてきてしまったか。
この2冊にから改めて感じたことです。
この2冊にから改めて感じたことです。
21世紀の資本
読書の日曜日
放射線を浴びたX年後
3月21日にグリーンイメージ国際環境映像祭に行ってきました。
3本見た映像の中で一番印象に残ったものを紹介します。
~放射線を浴びた~X年後
1954年のビキニ環礁で行われた水爆実験を追ったもの。
一連の出来事に対する葬り去り方。
被害を受けた方のあきらめ感。受け入れざるをえない状況。
被害を受けた方のあきらめ感。受け入れざるをえない状況。
数は少ないですが、今後も自主上映が行われるようです。
ぜひご覧ください。
ぜひご覧ください。