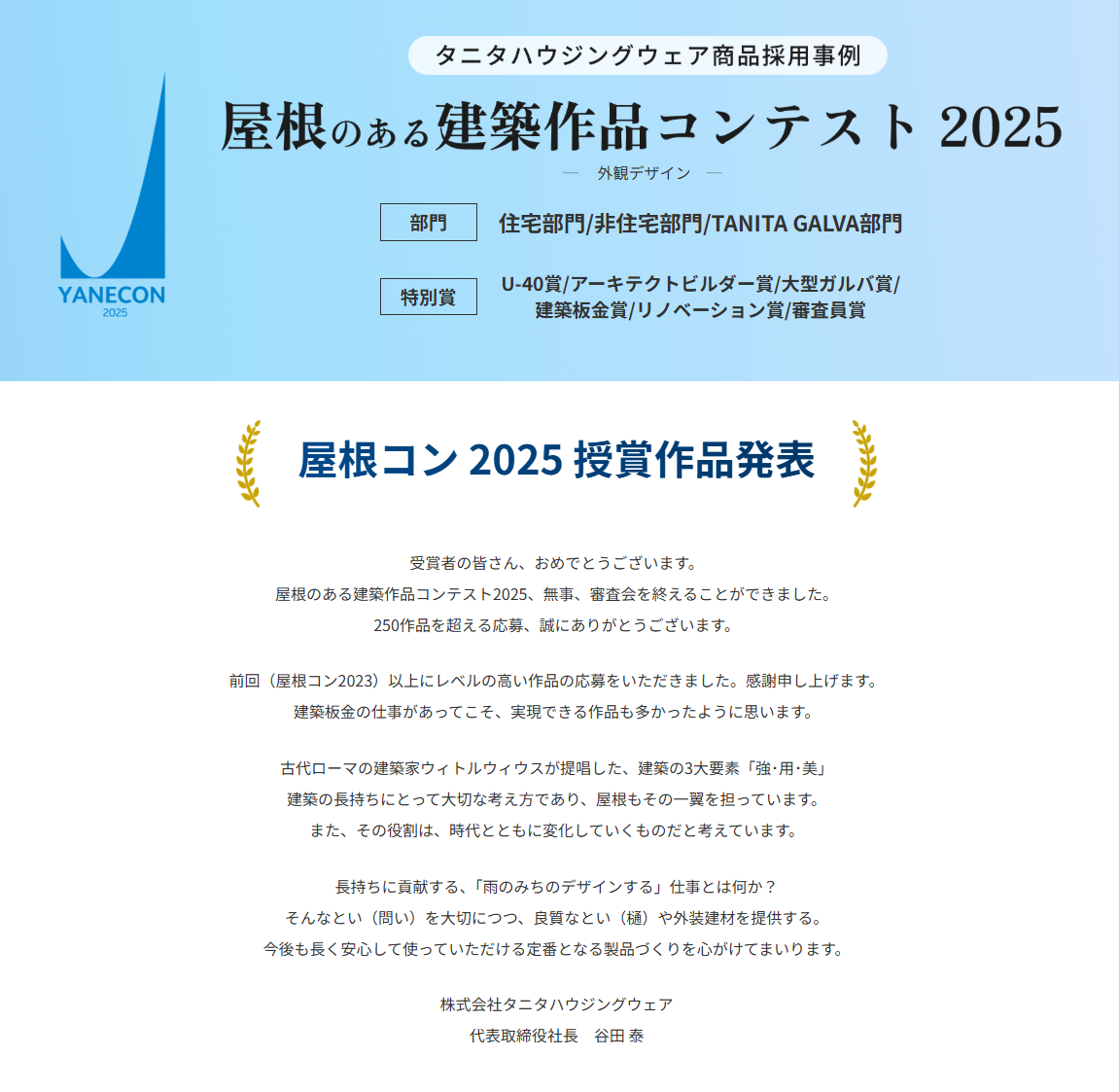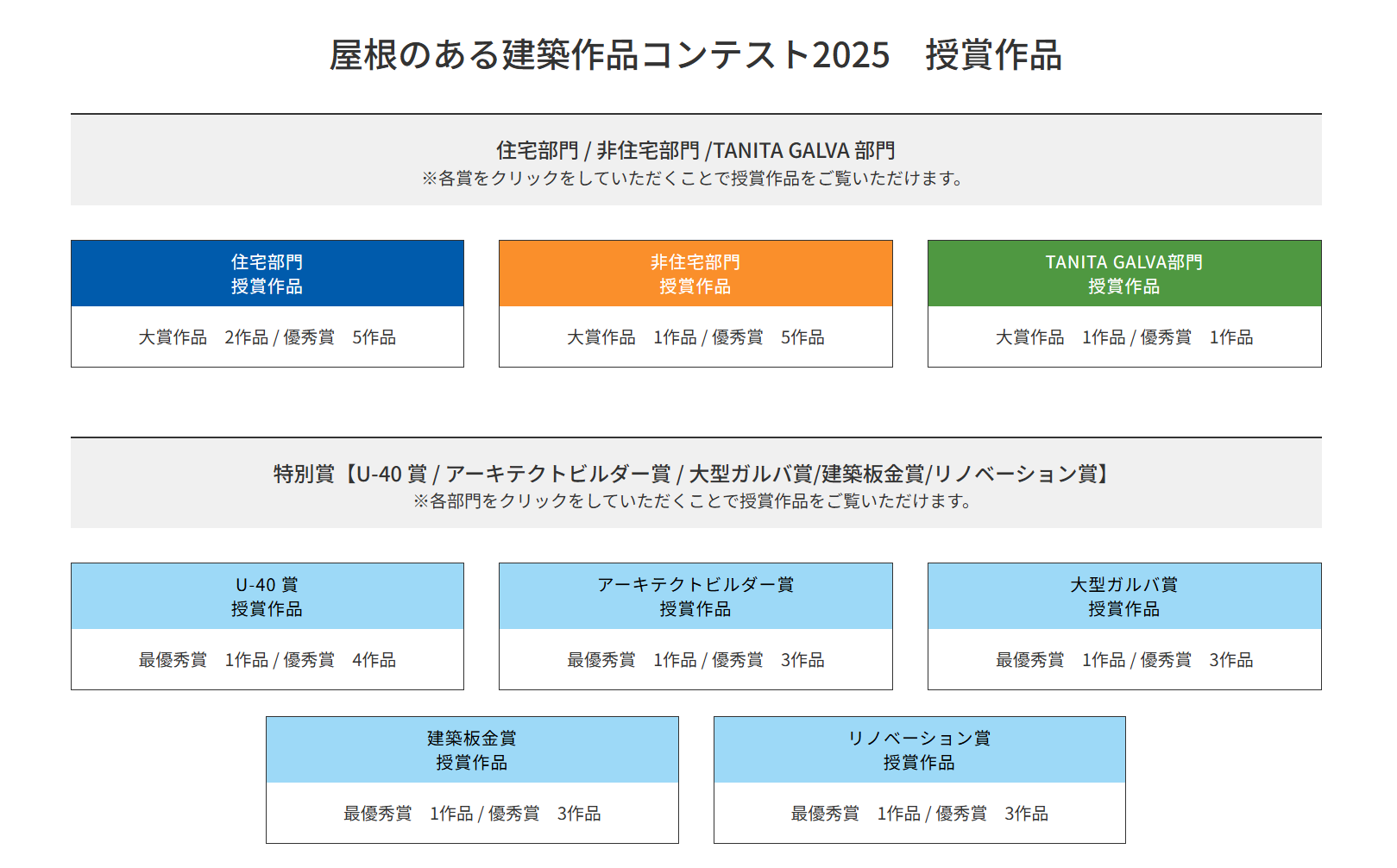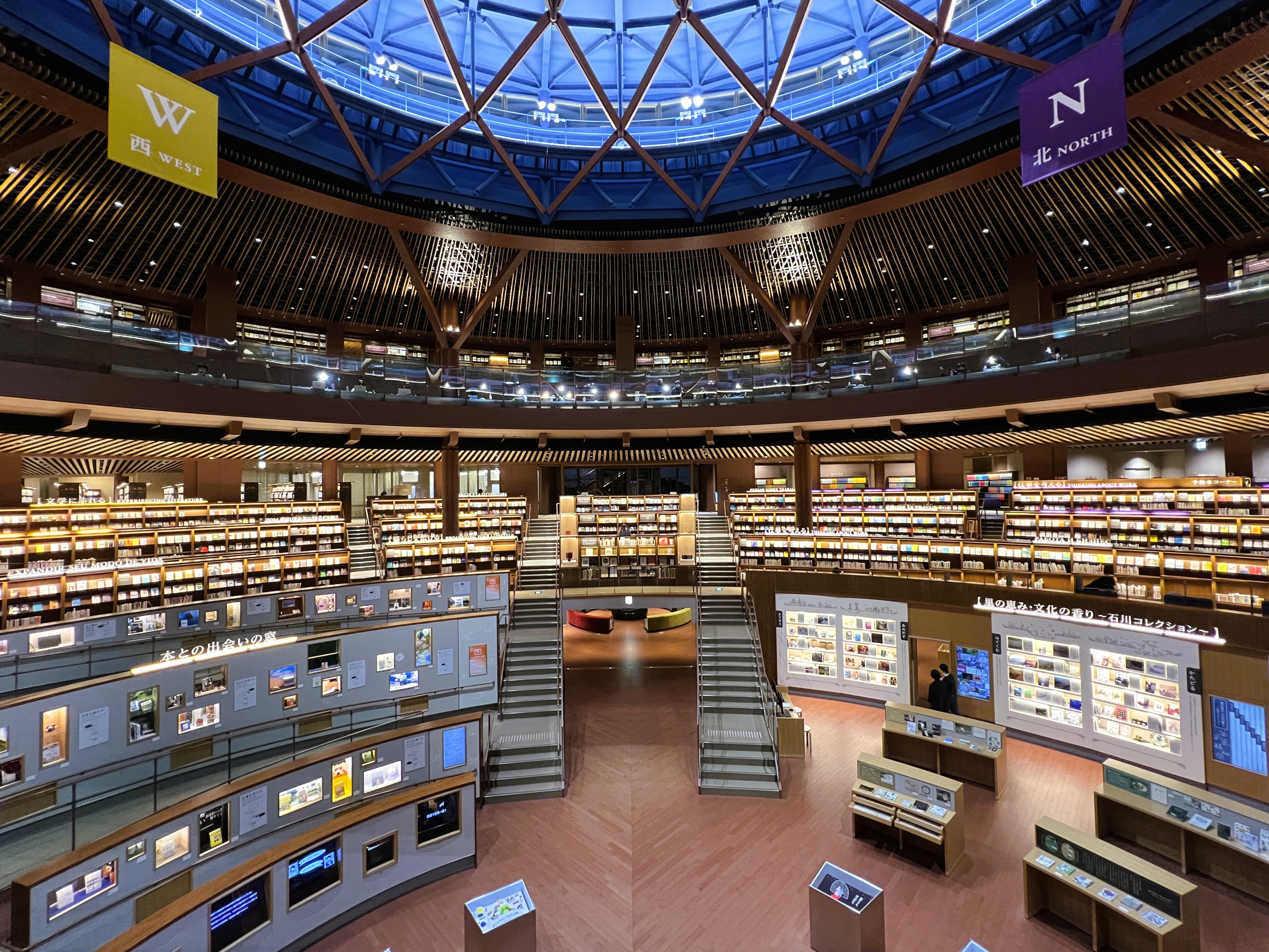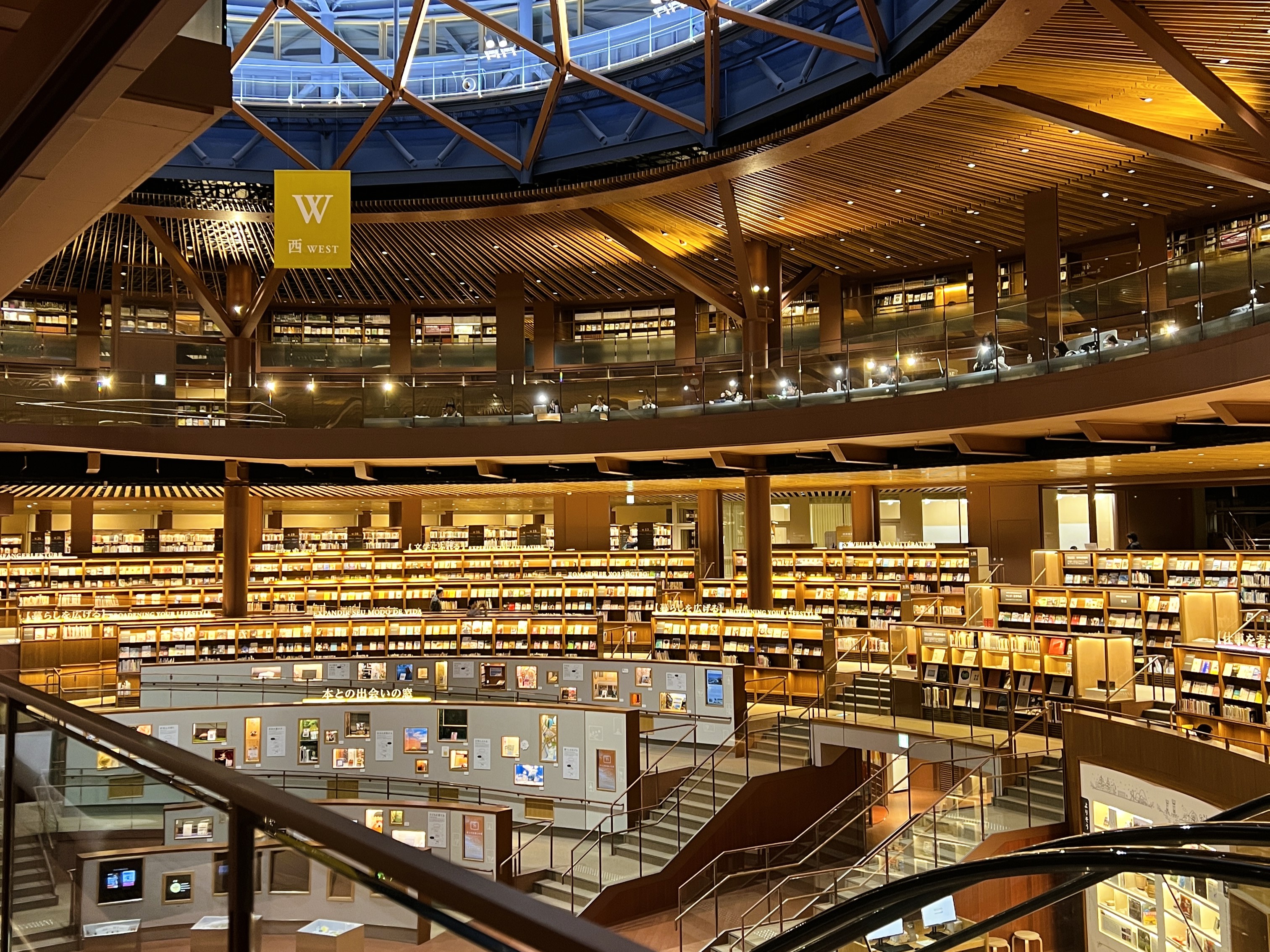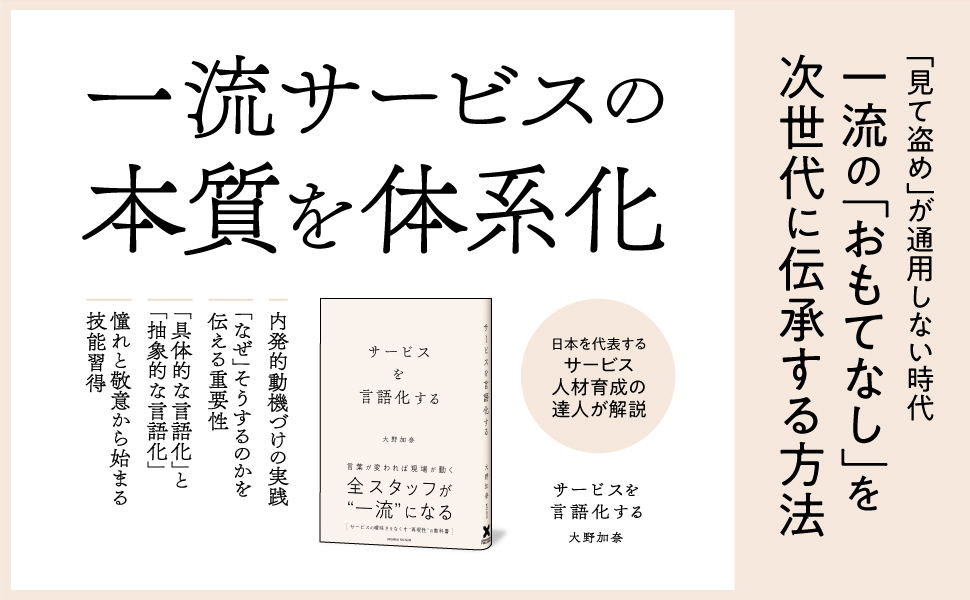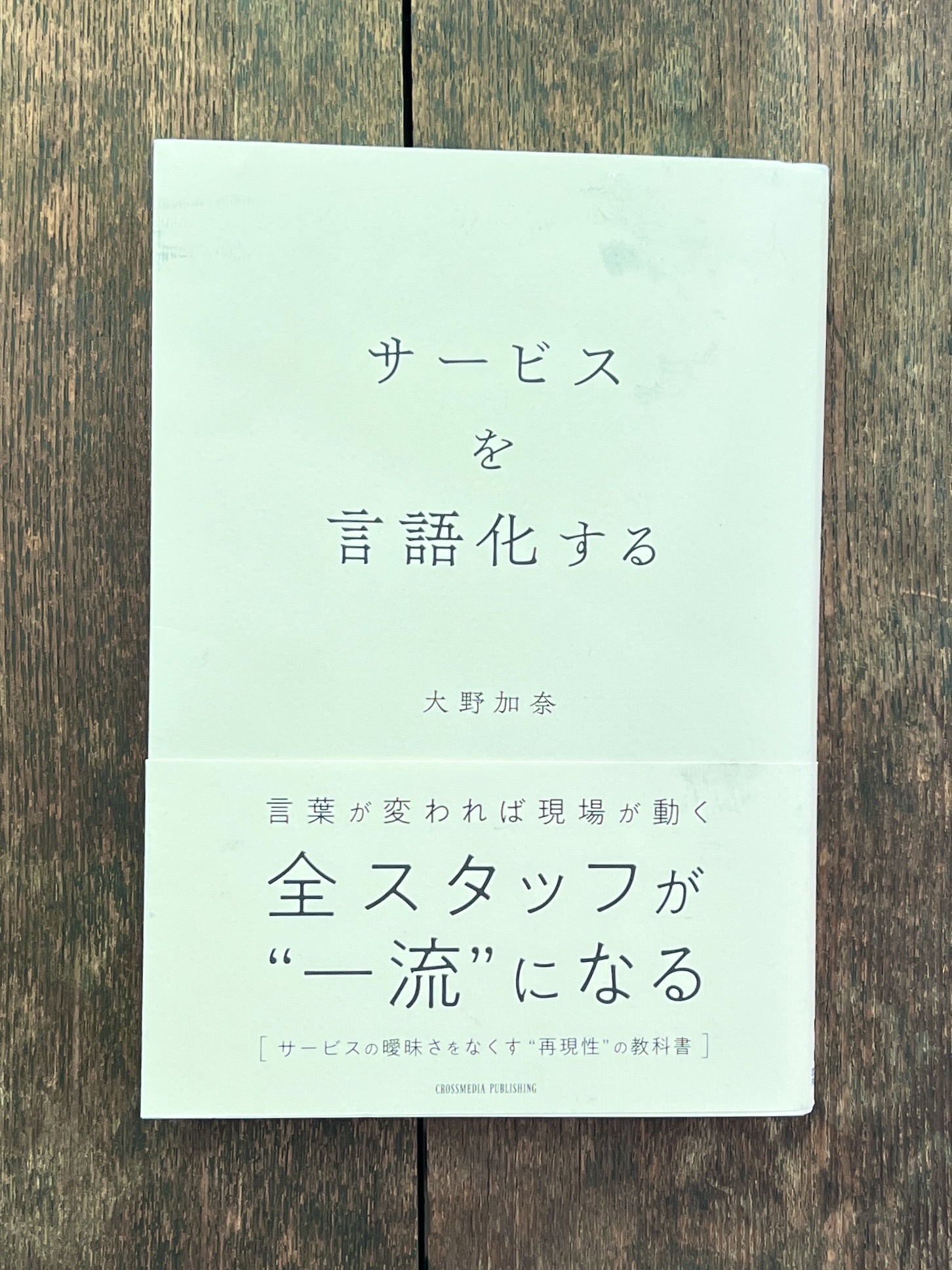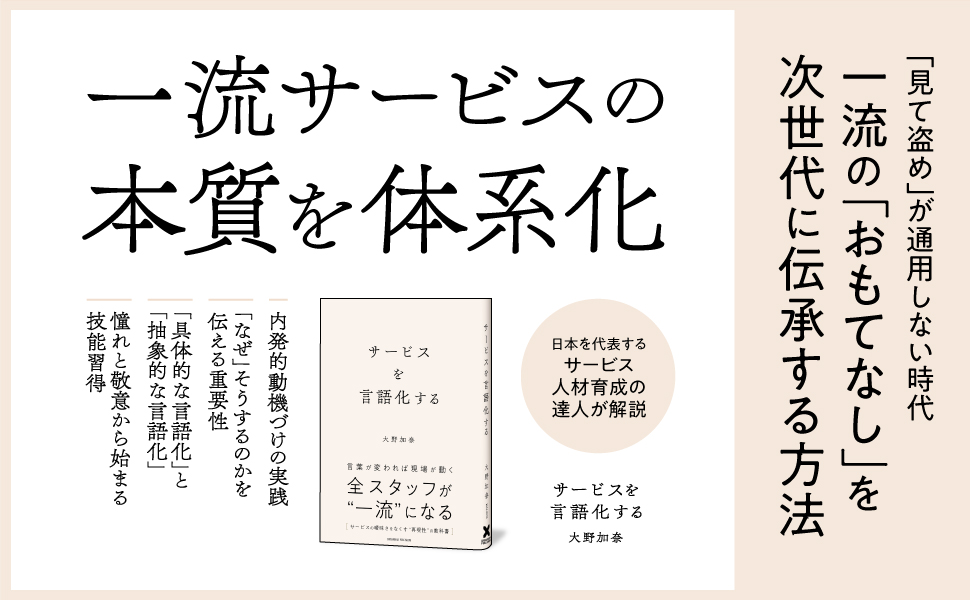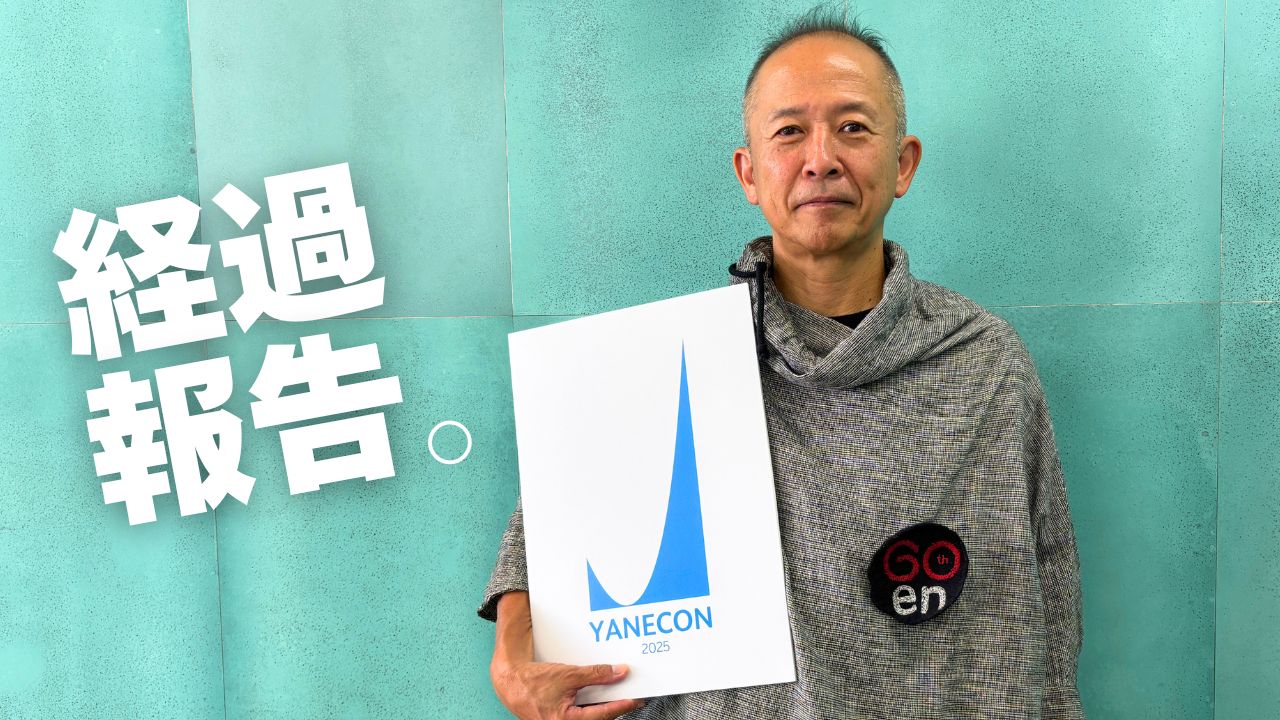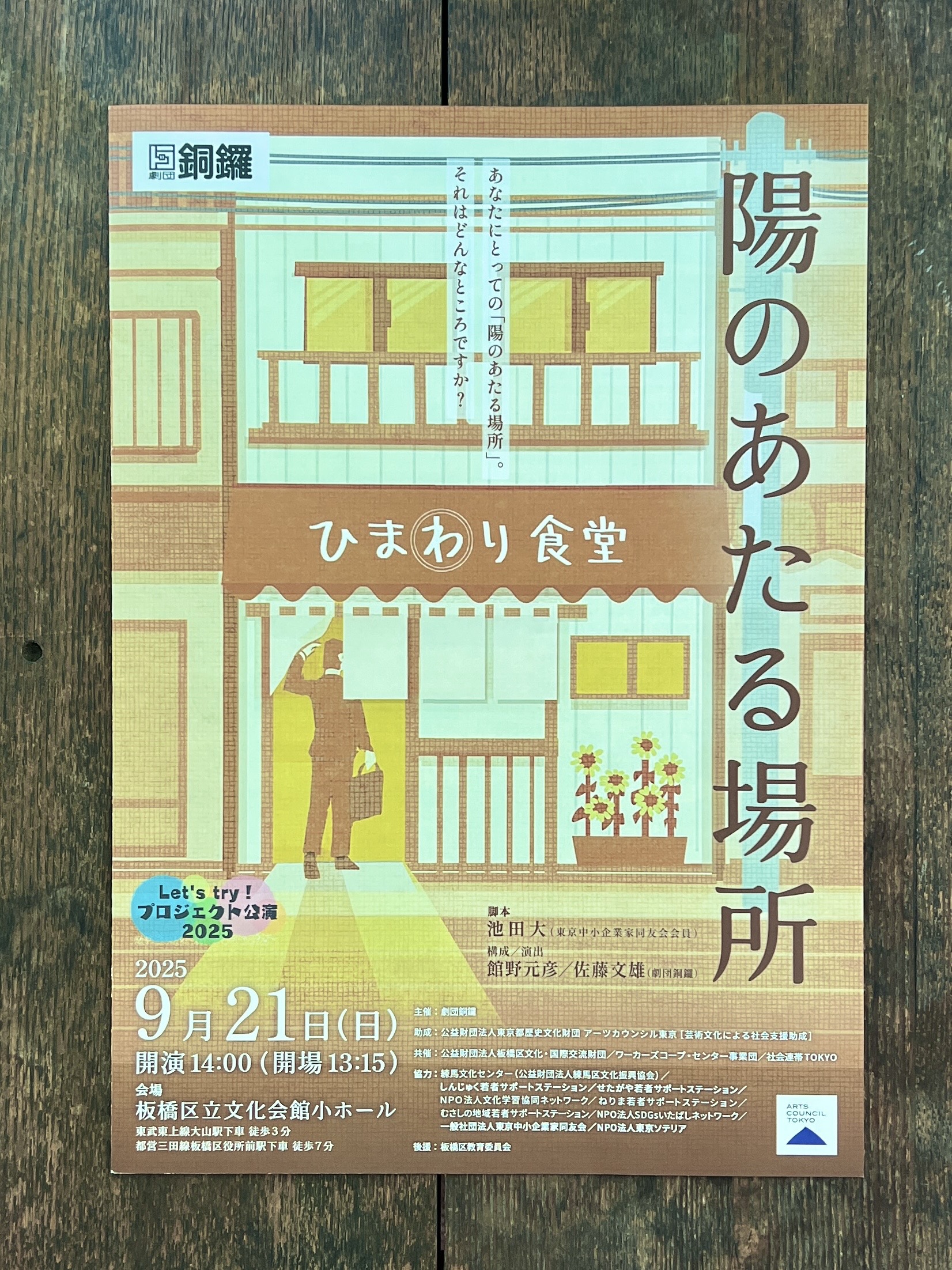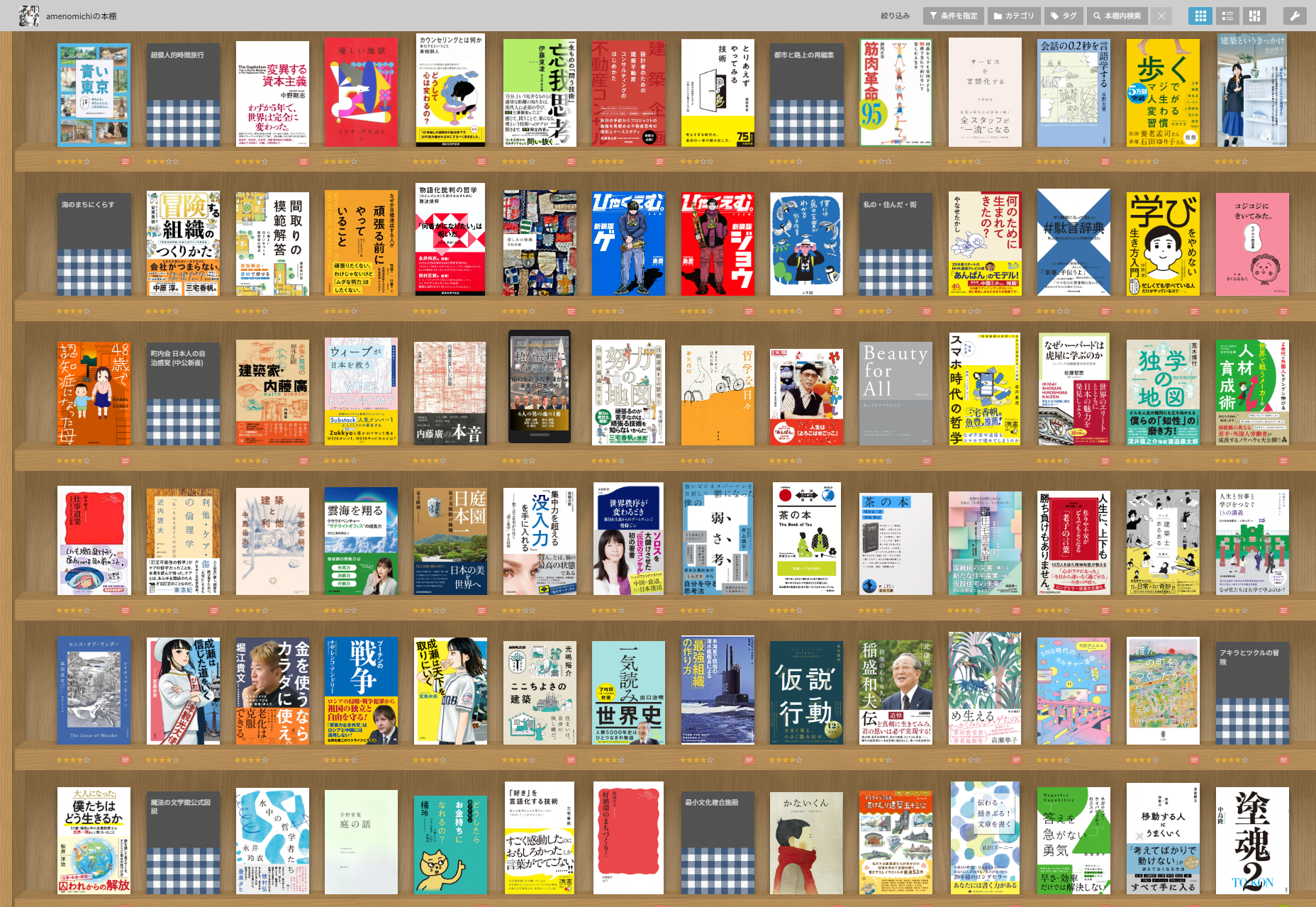
1番下段の 庭の話 から 青い東京 まで
読了した本が74冊 例年よりちょっと多めかな
これ以外に積読本も多数あります
ここ数年は哲学的なものを手に取る機会が多い
私が参加している読書会でもその傾向があります
日本の経済についてもいろいろ考える1年だったように思います
特にインフレ経済に慣れていないことを自覚しました
Beauty for ALL
美しさは誰のもとにもある お金でしか得られないものではない
歩く
靴を3足購入 ほぼその靴しか履かなくなりました
父がこの本を購入して読んでいることにビックリ
歩けることって大切ですね
冒険する組織
多様で答えのない社会では一步踏み出すことが大切
Good Job よりも Nice Try が求められています
カウンセリングとは何か
作戦会議:生活を回復するための科学的営み
冒険:人生のある時期を過去にする文学的な営み
近代の根源的なさみしさの中で
正直に、率直に、本当の話をすることを試み続ける場所
自由に自分らしく生きるってなかなか難しい
だからこそ一人ひとりをキャリアを大切に考えたい
今年もどのような本に出会い、考えや行動が変化するか楽しみです

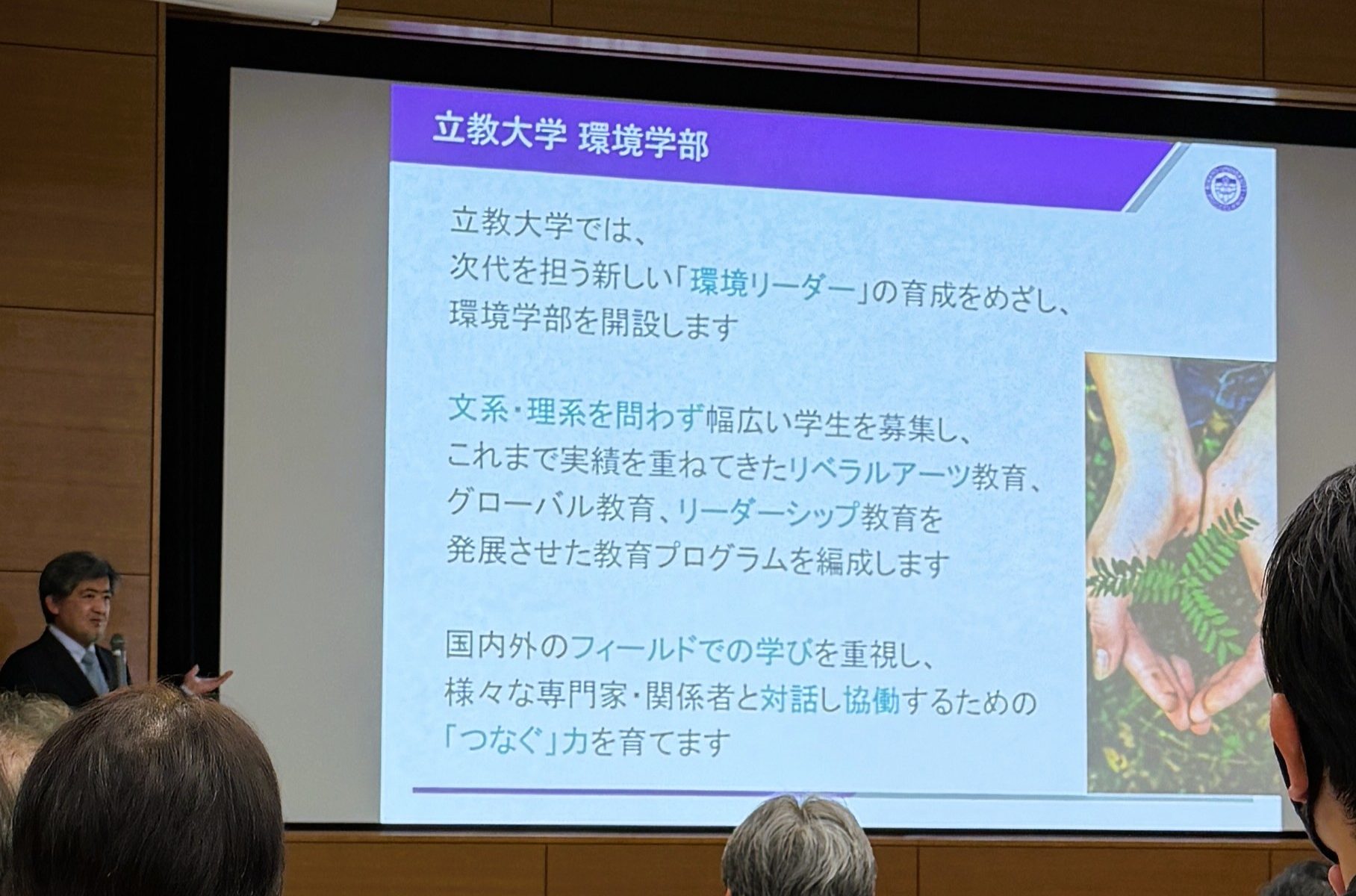
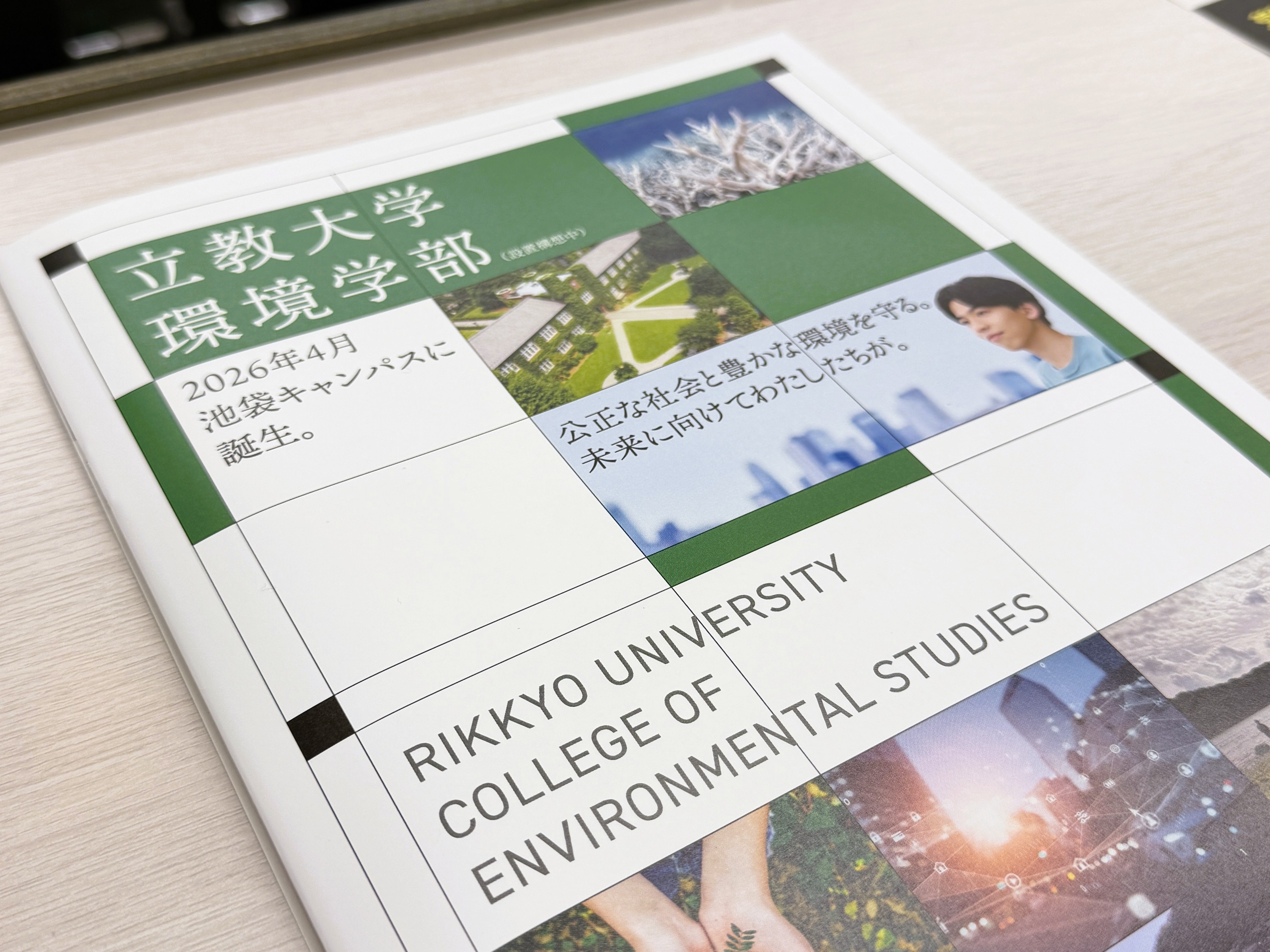


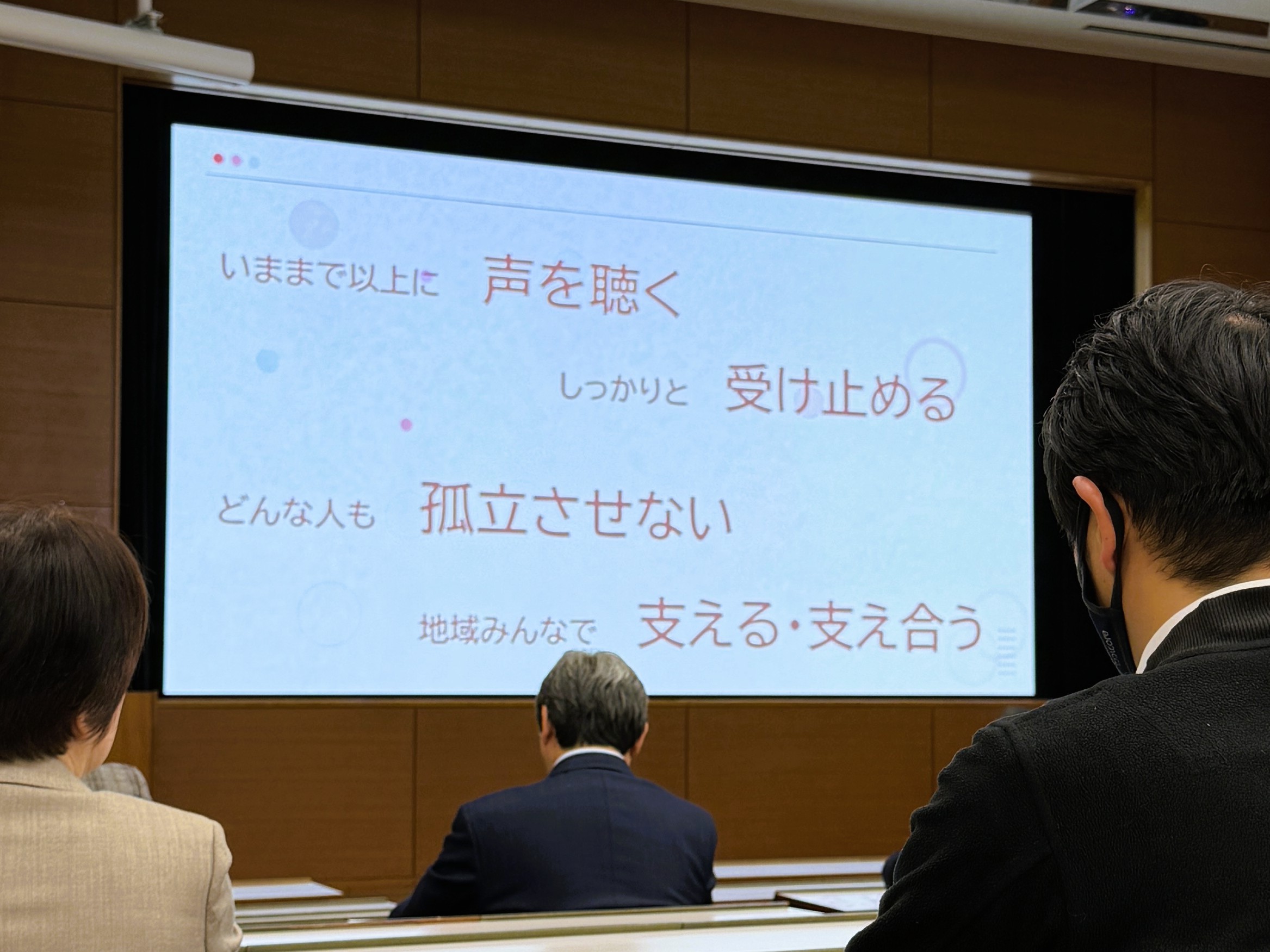

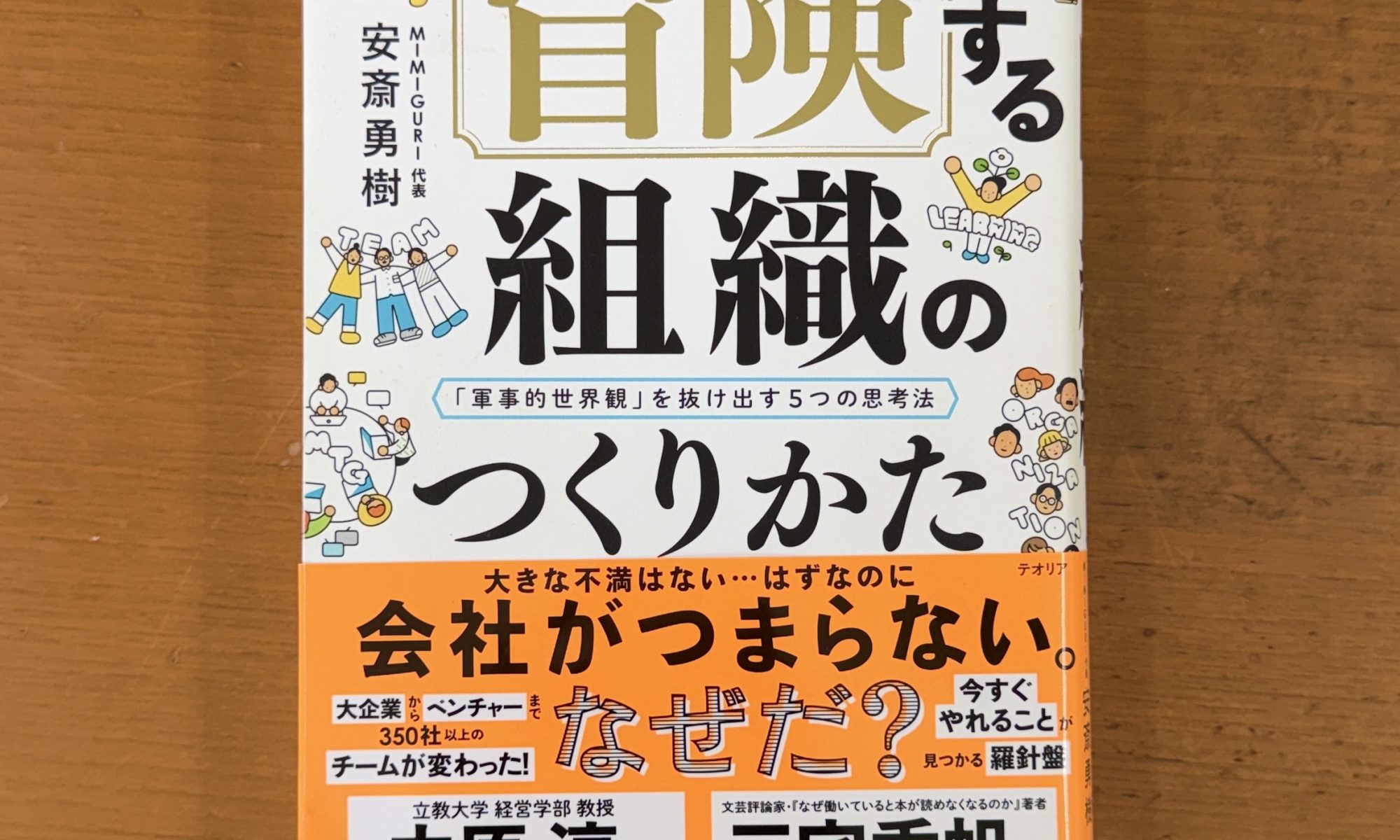
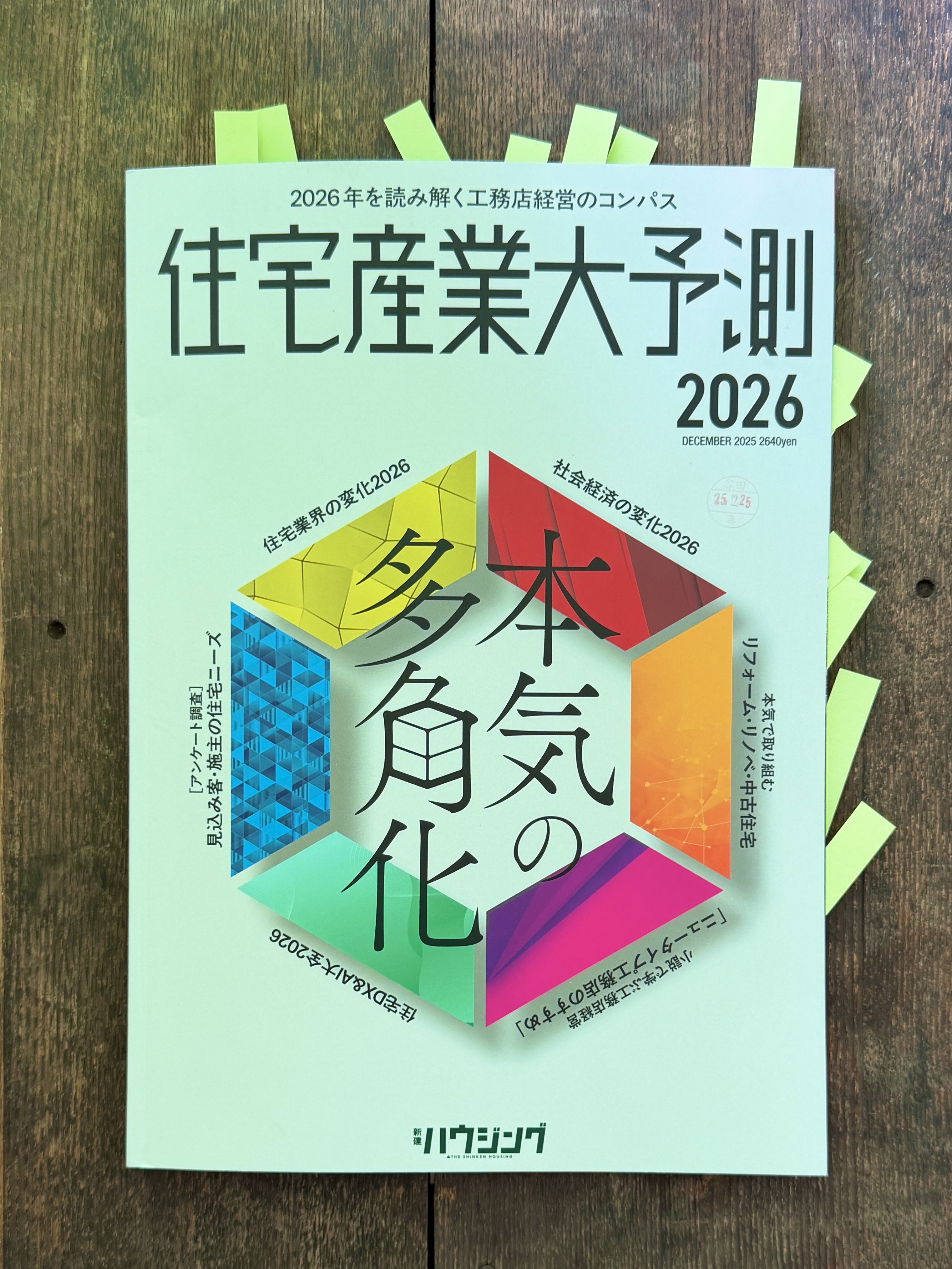
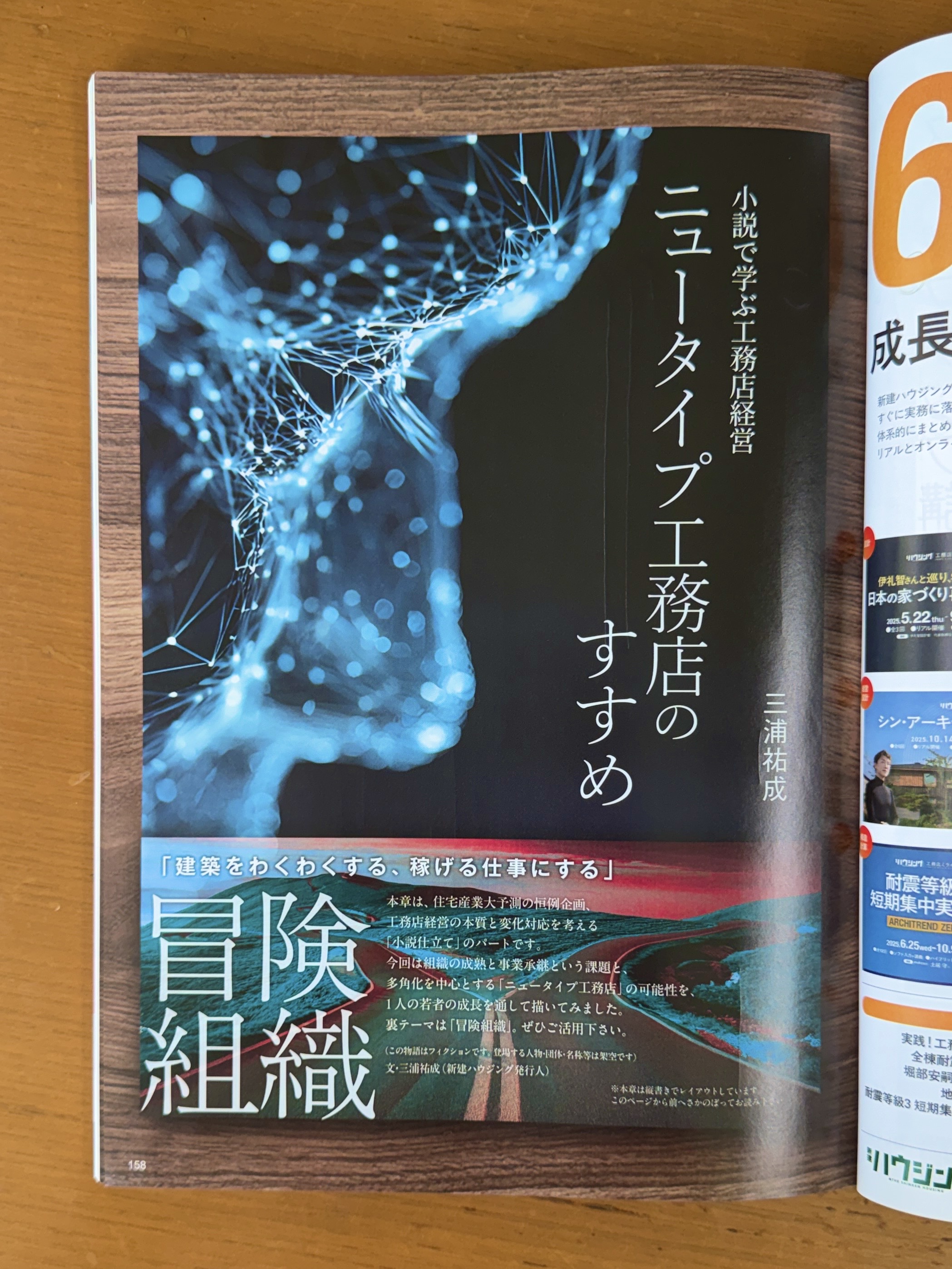

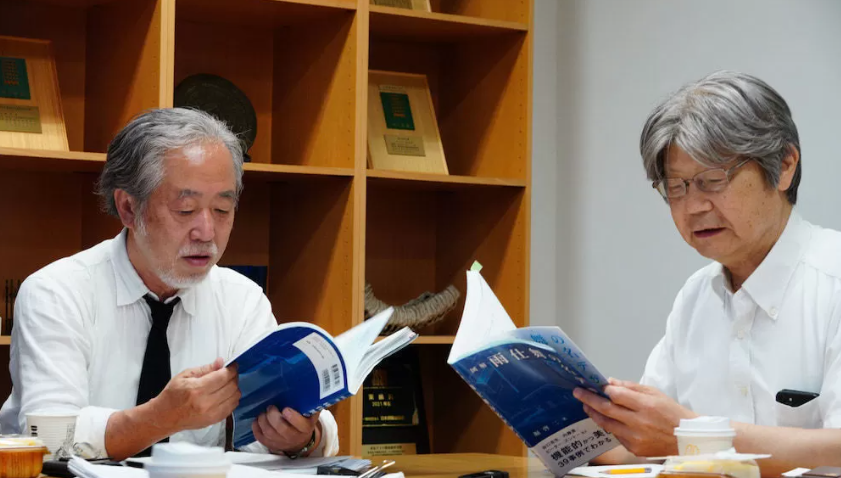
 昨年7月に収録し、12月に
昨年7月に収録し、12月に